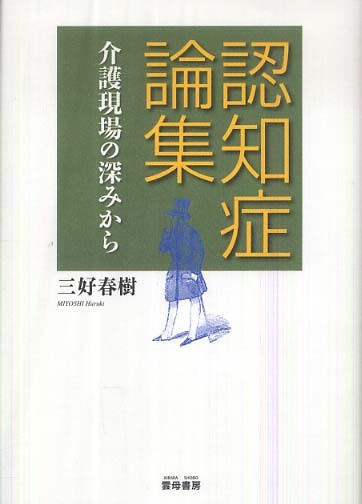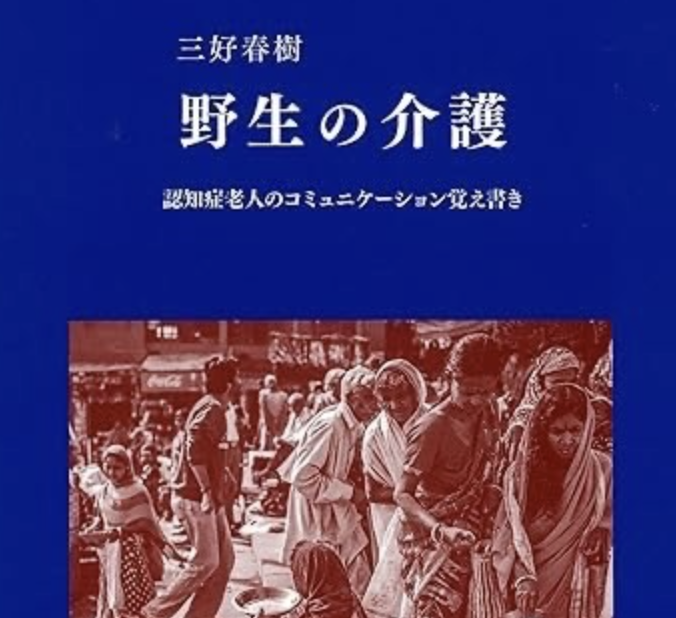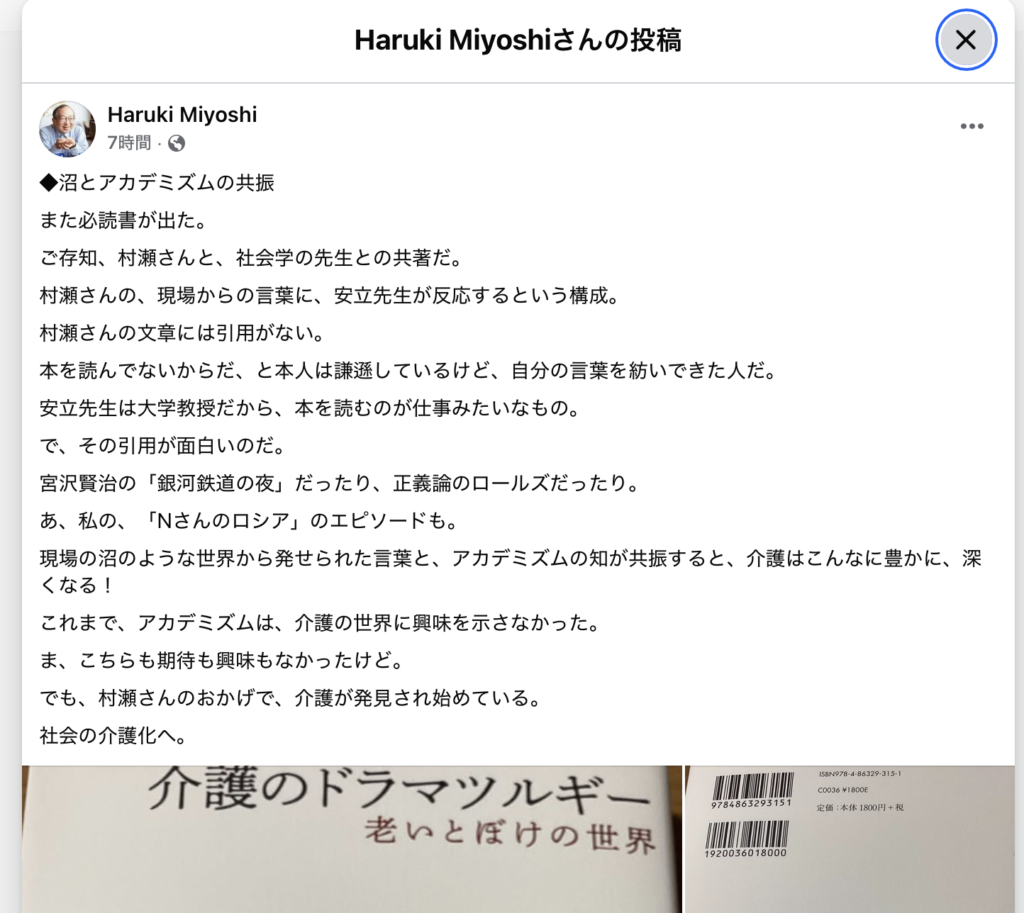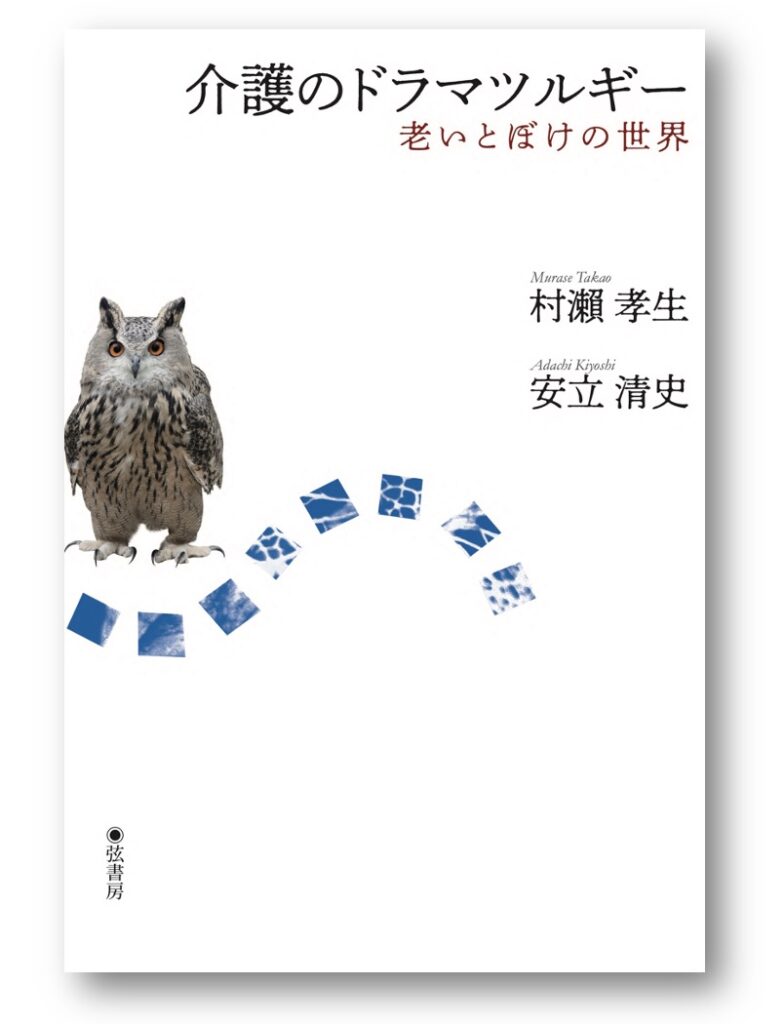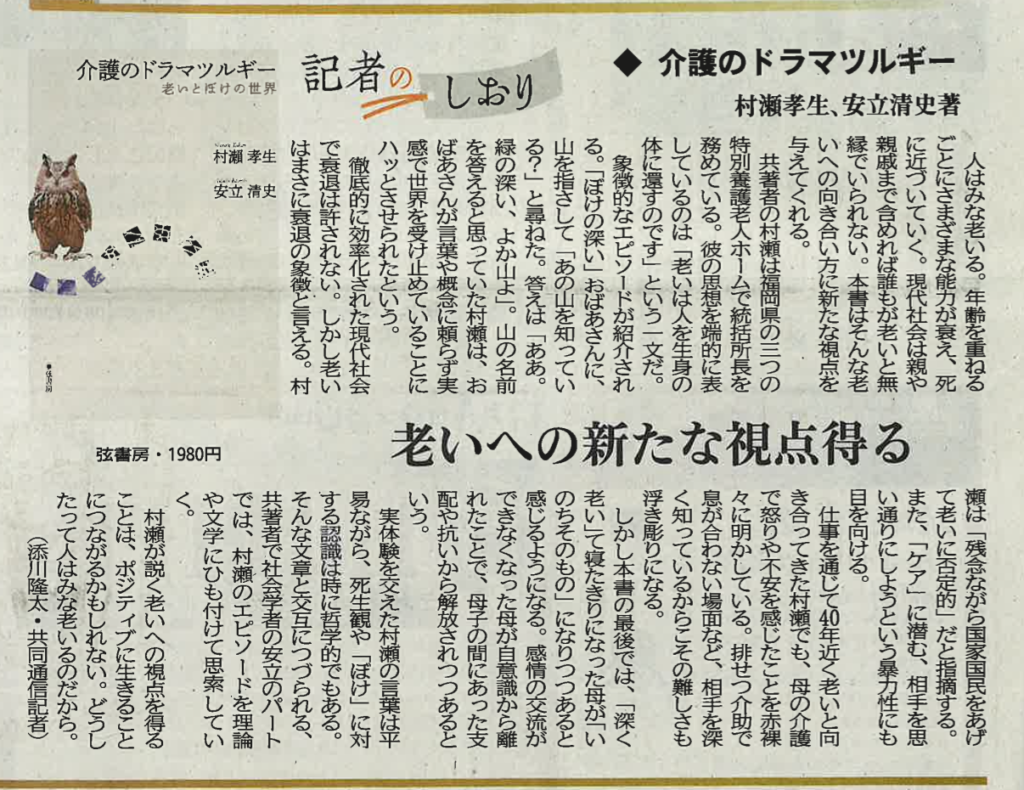三好春樹さんを読む(3) 「Nさんのロシア行き」
1
心理学と社会学とは、近いようで遠い。看護と介護もそうかもしれない。社会学の中でも、個人から始めるのと社会から始めるのとで、方法的個人主義と方法的全体主義という対立がある。そんな中で一見すると中間あるいは折衷のように見えるのがマックス・ヴェーバーの「理解社会学」だ。当事者が行為にこめた意味を「理解」することが必要だ、というのだ。でもこの「理解」がよく分からなかった。それが、三好春樹さんの本で「Nさんのロシア行き」のエピソードを読んだとき、はっと気づいた。このことではないか、と。調べてみると三好さんは1984年の『看護学雑誌』に「Nさんにとっての〈ロシア〉—隠喩としての老人の言動」という論考を発表している。もう40年も前のことだ。当時、認知症高齢者の行動の意味をまともに受け止めて考えようとする人などいなかったのではないか。
2
このエピソードは多くのことを考えさせる。認知症の初期に「家に帰ります」といって施設やデイケアから抜け出していく高齢者たちは数多い。施設の側は脱出して「徘徊」する人たちは、見当職を失って混乱している(だけ)と考えたに違いない。むかしながらの老人病院を見学した時のこと──病院には「徘徊」のための長い回廊が設けてあった。まるでハツカネズミの飼育ケージのように。行動だけみて、「徘徊」に内的意味世界があるなどと考え付きもしなかったのだろう。
3
Nさんのロシア行きは、看護とは違う「老人介護」を、三好春樹さんが「発見」した最初期の記録ではないかと思う。三好さんの開拓した「徘徊に出ていく老人を止めるのではなく、いっしょに歩いてついていく」という方法は、いま考えてもラディカルだ。可能なのに不可能と思えてしまうこの方法。だからコペルニクス的な転回を思わせる。専門職はその専門性ゆえ、誰もやってみようと思わなかったのかもしれない。しかし福岡の「宅老所よりあい」では地道に実践されてきた。村瀨孝生さんの著作の中にも、どこまでもいっしょに歩いて行って途方にくれるエピソードが、たびたび登場する。なかでも「ヨシオさん」のエピソードは突出している。自宅では新聞を逆さまに読んでいる。「徘徊」についていくと、書店に入って本を逆さまに並べなおす。さらに驚くのは、蕎麦屋にはいったあと、その厨房の奥にまでずんずん入っていって裏口から出ていくというのだ。「よりあい」の職員や村瀬さんたちを翻弄し疲労困憊させたうえ、見失ってあたふたする村瀬さんがようやく見つけて安堵の気持ちでハグしようとすると、するりとよけて、先を急ぎます、とさらに歩いていく。こうしたエピソードを読むと、抱腹絶倒したあとで、社会学の考えている「社会」などするりと抜け出て、「この社会の枠組みを突破する人」を見たような気がする。頭で考えたラディカルさではなく、身体から滲みでるラディカルさである。まるで、その先に《もうひとつの社会》があると行動で表現しているようだ。この人たちからは「社会」という概念や束縛が消えうせている。意図しない自由でアナーキーな姿が浮かび上がる。三好春樹さんは全共闘世代の人だから、全共闘世代が意識でやっていたことを、Nさんは身体でやっているように見えたのかもしれない。
*三好春樹、2009、『認知症論集─介護現場の深みから』、雲母書房