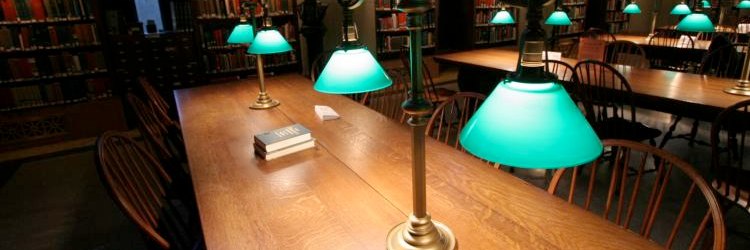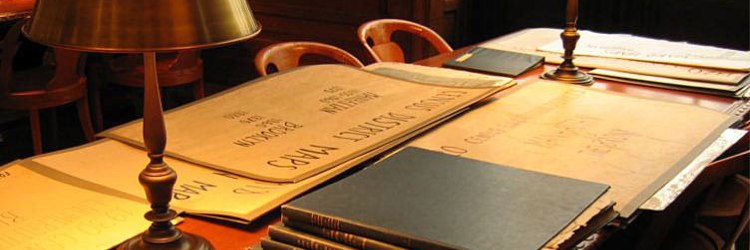十年ぶりくらいで唐津に家族旅行しました。かつては留学生をつれて秋の唐津くんちによく行ったものでした。博多の山笠は賑わいすぎて遠くから見物するかんじですが、唐津くんちは、ほんとうにすぐ触れるような近くを巡航していきます。唐津にいくと鰻の竹屋に行ったものですが今回は予約が取れませんでした。夏のこの時期、予約はとりにくいそうです。骨せんべいだけ買って帰りました。今回の収穫は、旅館・洋々閣のギャラリーを見学できたことです。唐津焼の中里親子の作品です。宿泊でないと中へ入れないかと思っていましたが、そんなことはなくとてもきさくに迎え入れてくださいました。おまけにジャック・マイヨールさんのとっておきのエピソードまで聞かせていただきました。