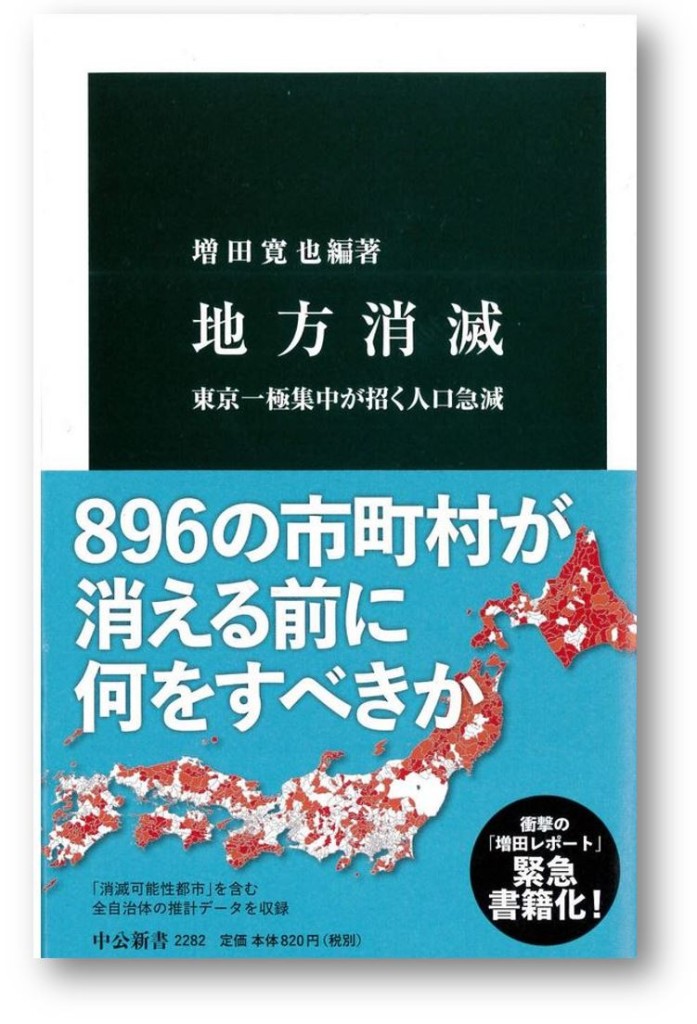インフォメーション
安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照


カウンタ
- 475620総訪問者数:
- 213今日の訪問者数:
- 225昨日の訪問者数:
最近の記事
- 3月14日に広尾の日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について話します
- 立命館大学・加藤周一現代思想センターの鷲巣力さんにお会いしてきました
- 世直しと立て直し(中井久夫)
- 「京都人の密かな愉しみ」を見る
- 3月に日本赤十字看護大学で『介護のドラマツルギー』について講演をします
- 「クレヨンハウス通信」の「落合恵子のBook Club」で『介護のドラマツルギー』が取り上げられました
- 「超高齢社会研究所」のサイトは1月末で閉鎖する予定です
- noteに「宅老所よりあい」における『介護のドラマツルギー』を投稿しました
- 熱中小学校10周年
- ドラマツルギーとは何か(『介護のドラマツルギー』解説)
- 日本農業新聞が『介護のドラマツルギー』を紹介してくれました
- 『介護のドラマツルギー』のブックトークを行いました
- 村瀨孝生さんと『介護のドラマツルギー』のブックトークを行います。
- 三好春樹さんを読む(その3) 「Nさんのロシア行き」
- 三好春樹さんを読む(その2)
- 三好春樹さんを読む(その1)
- 西成彦さんの「内村鑑三の『デンマルク国の話』を読む」
- 三好春樹さんが、村瀬さんと私の共著『介護のドラマツルギー』を高く評価してくださいました
- 共同通信による全国の地方新聞への『介護のドラマツルギー』の紹介の配信
- 芥川賞作家・村田喜代子さんが『介護のドラマツルギー』を取り上げてくれました
- noteで『介護のドラマツルギー』についての解説しました
- 西日本新聞のシニア欄で『介護のドラマツルギー』が紹介されました
- 村瀨孝生さんとブックトークをしました(9月27日、福岡ユネスコセミナー)
- 老いとぼけの自由な世界(村瀨孝生+安立清史)
- 「よりあいの森」訪問から10年
- 長湯温泉・ラムネ温泉
- 野崎歓さん「100分de名著」でサン=テグジュペリ『人間の大地』を解説
- ハンガリーのアニメ「名画泥棒ルーベン・ブラント」を観ました
- 村瀨孝生さんの「老人性アメイジング! 寿ぎと分解」YouTubeで公開中
- 村瀨孝生・安立清史『介護のドラマツルギー/老いとぼけの世界』(弦書房)
- 「老いとぼけの自由な世界」村瀨孝生さんの講演
- 村瀨孝生さんとの共著『介護のドラマツルギー』が出版されます。
- 在宅医療の新しい流れに学ぶ──在宅ホスピスの二ノ坂保喜先生との対話
- 二ノ坂保喜先生の講演と対談
- CS神戸の中村順子さんにお会いしてきました
- 日本NPO学会大会(関西学院大学)で報告
- 関西学院大学で開催される日本NPO学会に参加します
- 映画「ピロスマニ」(1969)を観ました
- 『福祉社会学研究』22号で拙著『福祉社会学の思考』が書評されました
- 日本NPO学会(関西学院大学)の企画パネルで討論者として登壇します
- ジブリ映画「君たちはどう生きるか」と花巻・大沢温泉
- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)
- 宮沢賢治ゆかりの大沢温泉(花巻)
- 小岩井農場の一本桜を見に行きました
- 藤の季節
- 『福祉社会学の思考』が『社会学評論』で書評されました
- 『社会学と社会システム』(ミネルヴァ書房)の12章を執筆しました
- 「ACAP 20周年」記念の「Active Aging Conference 2025」
- 「ことばの呪文からどう脱出するか」(香川県丸亀市講演)
- 30年ぶりに原宿を歩く
- ヴァーチャル坂本龍一
- 「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」を観に行く
- 香川県・丸亀市で講演します(2025/3/2)
- CareTEX福岡’24 専門セミナーの講演動画
- 頌春2025
- 中村学園大学で『ボランティアと有償ボランティア』の講義をします
- 「第一宅老所よりあい」をたずねてきました
- 山岡義典さんから『福祉社会学の思考』のご感想をいただきました
- 唐津小旅行
- 梅雨明けの虹でしょうか
- 福岡の「第二宅老所よりあい」
- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評
- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました
- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評
- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)
- ジャカランダの花
- 図書館奇譚
- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します
- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました
- 長湯温泉(その2)
- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)
- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します
- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉
- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る
- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉
- 「無法松の一生」を観る
- 大濠雲海
- 博多で講演と対談をしました
- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました
- Chat GPTに論争をふっかける
- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎
- 福岡の桜、一挙に満開
- 福岡の桜開花(3/27)
- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます
- 福岡城跡の仮設・天守台
- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー
- 福岡・桜祭り
- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催
- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催
- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告
- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問
- 認定NPO法人・市民協の理事会
- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行
- ボストン・シンフォニーの小澤征璽
- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒
- 加藤周一、座頭市を語る
- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史
- ジブリ・加藤周一・座頭市
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2009年8月
- 2008年10月
- 2008年8月
- 2006年8月
- 2005年8月
- 2004年8月
Count per Day
- 597983総閲覧数:
- 222今日の閲覧数:
- 238昨日の閲覧数:
- 「銀河鉄道の夜」と「千と千尋の神隠し」
- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん
- プロフィール
- 「宅老所よりあい」の下村恵美子さん引退。「よりあいの森」にて(8/31)
- 「京都人の密かな愉しみ」製作統括の牧野さんがゲスト・スピーカーに
- 鈴木清順の「陽炎座」(1981)を観る
- 最終講義のスタイル
- 三島由紀夫主演の映画「からっ風野郎」を観る
- 沢木耕太郎の社会調査法講義
- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)
- 「生きる」と「ゴジラ」と三島由紀夫
- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて
- 新世紀エヴァンゲリオンにおける「使徒」は「台風」のメタファーか
- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く
- 日本社会事業大学(旧・原宿キャンパス)
- 著書、共著など
- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問
- 「天空の城ラピュタ」のような巨大な雲
- 宮沢賢治の墓所と枝垂れ桜(花巻)
- 『風立ちぬ』の家-夏目漱石の旧居
カテゴリー
- トップ (1,717)
安立清史のホームページとブログ