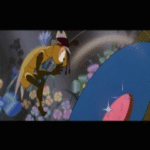8月15日が近づき「日本のいちばん長い日」(岡本喜八、1967版)をみました。2時間半以上の大作です。驚いたことにシネラでこんなに多くの観客をみたことがない、というくらいに多数の観客がつめかけていました。長いけど長くない。行き詰まる緊張。三船敏郎の阿南陸軍大臣が抜群にいい。ついで笠智衆の鈴木貫太郎首相。そして反乱軍の中心人物を演じた中谷一郎。
2015年版も話題のようですが、この岡本喜八版もすごいですね。1945年8月14日から15日にかけて、こんな226事件のようなことが起こっていたのか。知らなかったことばかりで驚きの連続でした。
ところで、この映画、全編「国体護持」を巡っての議論と攻防戦なのですが、まったく出てこないのが、戦争責任や苦しみに苦しみぬいた国民への謝罪の意識。最後の最後まで「天皇の戦争」で、国民なんか意識の中にはなかったということでしょうか。国民への謝罪もないのだから、当然、アジア諸国への謝罪もない。それが戦後70数年たっても、アジア諸国との軋轢として尾を引いていますね。
ところで、この映画、昭和天皇も見たそうです。どんな気持ちで見たのでしょうか。
映画の中では、ポツダム宣言を受け入れるかどうか、つまり「敗戦」を受け入れるかが問題なのに、陸軍は「本土決戦」をちらつかせながら、どう敗戦でなく「終戦」と言いかえるかを真剣に議論しています。その結果、客観的にみれば「敗戦」なのに、主観的には「終戦」になっています。このねじれが、現在にいたるまで、日本の戦後処理の問題になりつづけている気がします。