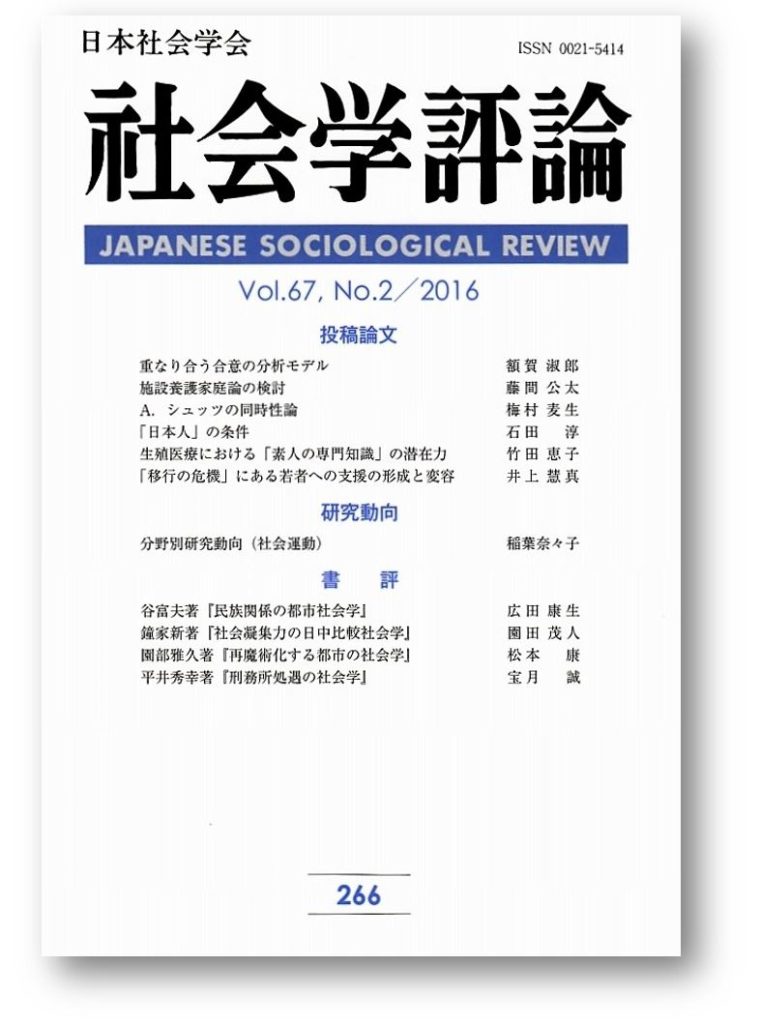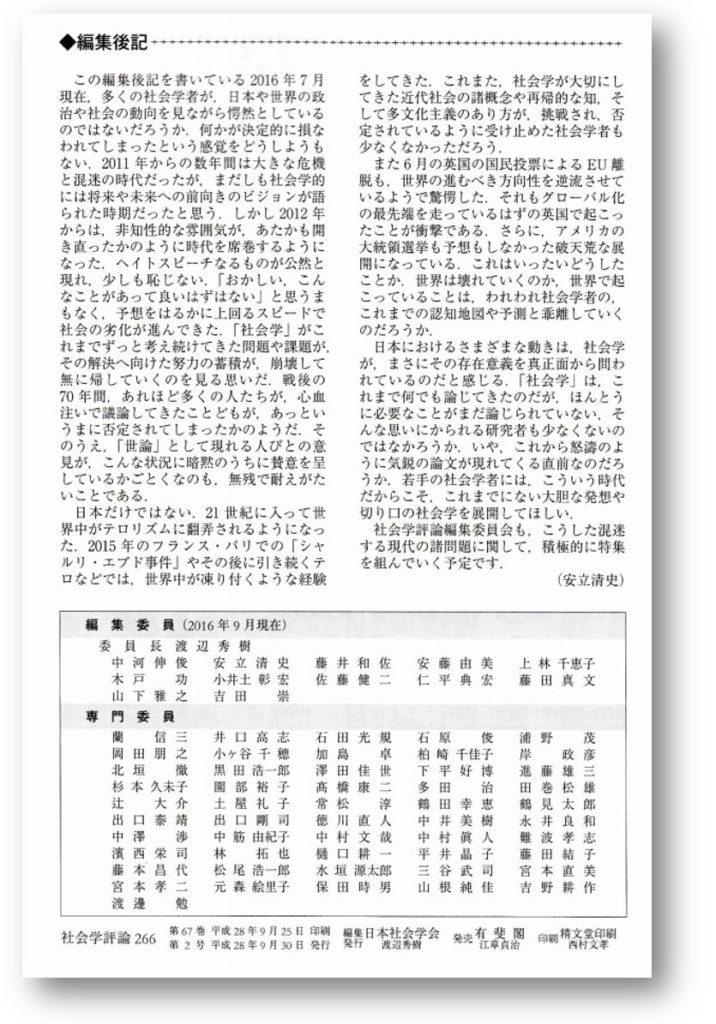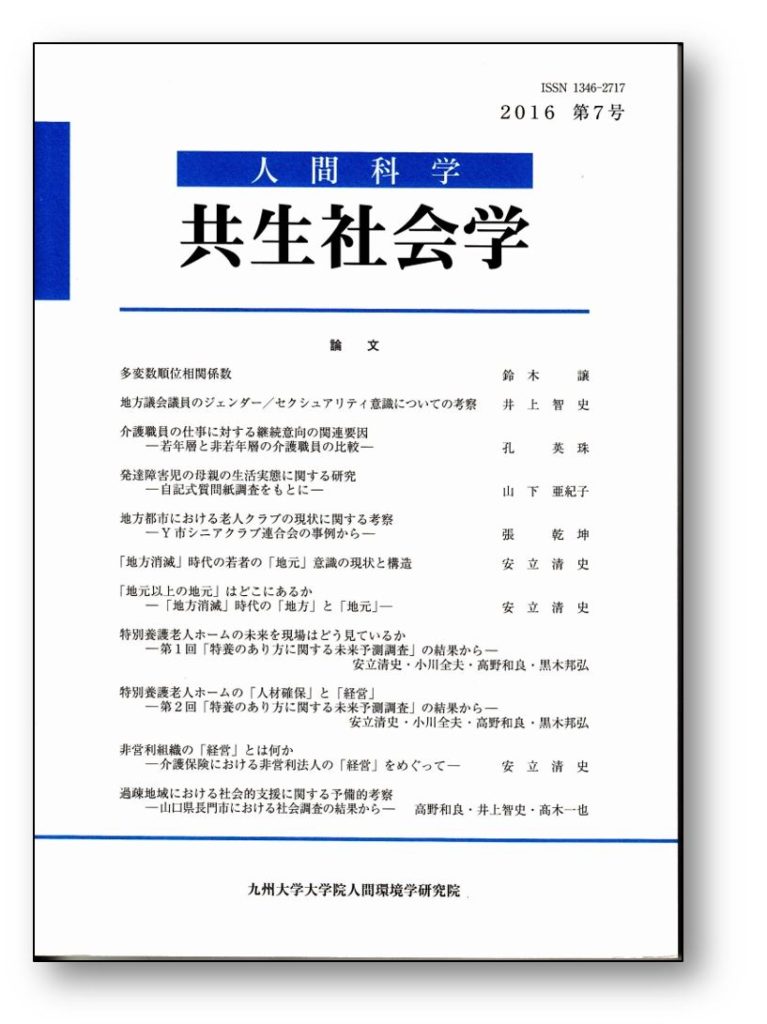おくればせながら、ようやく「シン・ゴジラ」をみました。すでに一日一回の上映になっており、観客が多いわけではありませんが、今年の夏の話題をさらった映画のひとつです。すでに多くの批評が出ているようですが、多くは、ゴジラを「3.11」と重ね合わせる(ゴジラをメルトダウンした原発と重ね合わせる)ものです。もちろんそういう寓意が込められていることは間違いないでしょう。でもそれだけではないと思います。
「シン・ゴジラ」には内面がない
考えてみたいポイントはいくつかあります。第1は「ゴジラの内面のなさ」です。伝説的な第一作のゴジラには、溢れるような怒りと破壊願望、そして破壊しても満足できない、やるせない悲しみのようなものが漂っていました。ゴジラがなぜ東京を破壊に来るのか、そこにはゴジラなりの深い内面があるように描かれていました。だからこそ、多くの観客を魅了し、多くの批評家に「ゴジラ論」を書かせたのでしょう(有名なところでは四方田犬彦や加藤典洋のゴジラ論などがあります)。ところが、今回のゴジラには、内面がありません。「エヴァンゲリオン」に心がないのと同じです。戦い、破壊するようには造形されているが、心は宿らない。そもそも心なんてない。そういうふうに造形されています。ここには注目しなくてはなりません。地震や津波、原発やその暴走、メルトダウンは「心」がそうさせたのではない。それはゴジラの怒りではない、ただの核物理現象だ、そう突き放しているようにも見えます。
SFではなく「ポリティカル・フィクション」
第2は「ポリティカル・フィクション」という見方です。これはサイエンス・フィクション(SF)ではない、ポリティカル・フィクションだという批評がでていました。なるほどと思いました。「シン・ゴジラ」をSFとしてみるとたいしたことはない。むしろ、ゴジラの血液凝固剤を、日本全国の工場が協力して生産する(軍事統制経済)ところや、省庁間の派閥や縦割りの弊害が、破滅的状況の中で、次第に克服されてひとつに連帯・団結していくという、普段にはありえない「ポリティカル・フィクション」の世界の展開に多くの時間と工夫がなされていました。子どもたちがこれを見て面白いと思うのだろうか。「セリフはほとんど理解できなかったけれど、面白かった」という感想があるらしいです。なるほど、現実の大人の世界をがんじがらめにしているフィクションみたいな日本のルールが、ゴジラによって破壊されていくのが痛快なんでしょうね。子どもたちだからこそ、この面白さが分かるのかもしれません。省庁間の縦割りのような、日常の力学が、ゴジラのようなスーパーパワーを前になすすべもなく崩壊していくのも痛快だし、狭い「縦割り」「たこつぼ」の中に閉じ込められていた「オールニッポン」の潜在力が、危機に瀕して、不死鳥のように蘇ってくるのも、子どもたちにはわくわくするところでしょう。ニッポンの力が試され、破滅しそうだが、ぎりぎりのところで立ち直る、という映画の世界のお約束が見事に成りたっていて、はらはらどきどきしたあと安心するんですね。ああ、やっぱり日本はいい国なんだと。でも、ちょっと中途半端なところもある。首相官邸は戯画的に描かれていて、あっというまに首相たちの乗ったヘリコプターは破壊され、みな死んでしまう。でも、肝心の「天皇」はどうなったのか。天皇は避難したのかどうか。第一作のゴジラでも最大の問題となった「1954年のターン」という問題提起(ゴジラがなぜ皇居を破壊せずにターンしてしまったのか)は、今回も曖昧にされたままでした。
ゴジラ対アメリカ
第3は「アメリカ」との関係です。第一作で、ゴジラが東京を破壊していくルートが、東京大空襲の時のB-29爆撃機と同じルートだということは、よく知られています。ゴジラは、その初めから、アメリカへの愛憎をともなって出現していたのです。そもそもゴジラはアメリカの「原爆」のメタファーでした。ゴジラはアメリカであり、ゴジラ映画とはアメリカと戦うという潜在意識を反映していたのです。さて今回はどうか。「アメリカであってアメリカでない」あるいは「アメリカではないがアメリカだ」というようなアメリカが登場します。大統領補佐官となった日系アメリカ人女性がそのように描かれています。この女性は意味深です。日本人の潜在的な抑圧と願望の投射なのでしょうか。実際に3.11にさいして、危機に瀕してなすすべもない日本、意志決定できない日本、それを見ていて介入しようとするアメリカがあったそうです。ゴジラ対日本は、ゴジラ対アメリカの代理戦争になるのでしょうか。
ゴジラは「グローバル資本主義」のメタファー
さて、以上をふまえて私の思うところを述べれば、ゴジラは「グローバル資本主義」のメタファーです。現代のゴジラは「グローバル資本主義」として突然やってきて巨大な力で荒れ狂います。そのあげく、日本を、東京をめちゃくちゃにしていくのです。地方は「地方消滅」します。しかし、日本政府は、この荒ぶる神を前に無力です。分析するほどに、真正面から戦って勝てる相手でないことが分かってくる。なんとか鎮めようと、その血液を「凍結」させ、一時的に破壊を止めさせるくらいが、せいぜいである・・・。ここには、現代の日本の「空気」というか「諦め」の気分が、濃厚に漂っています。かつてはゴジラと真正面から戦って打ち倒したものです。現在は、ゴジラ(というグローバル資本主義)と真正面から戦って勝てるはずがない、とはじめから諦めているのです。これは正確に日本の「空気」を反映しているのではないでしょうか。
グローバリズムや「グローバル資本主義」こそが、現代のゴジラである。新のゴジラであり、真のゴジラである。それは人間の心は通じないのです。「グローバル資本主義」はあたかも「God」の装いすら帯びている。このゴジラに対して、信仰を持たない私たちは、このような「God」を肯定はできず、かといって否定もできない中途半端な対応をするのみ。
ああ「シン・ゴジラ」は現代の私たちそのものです。