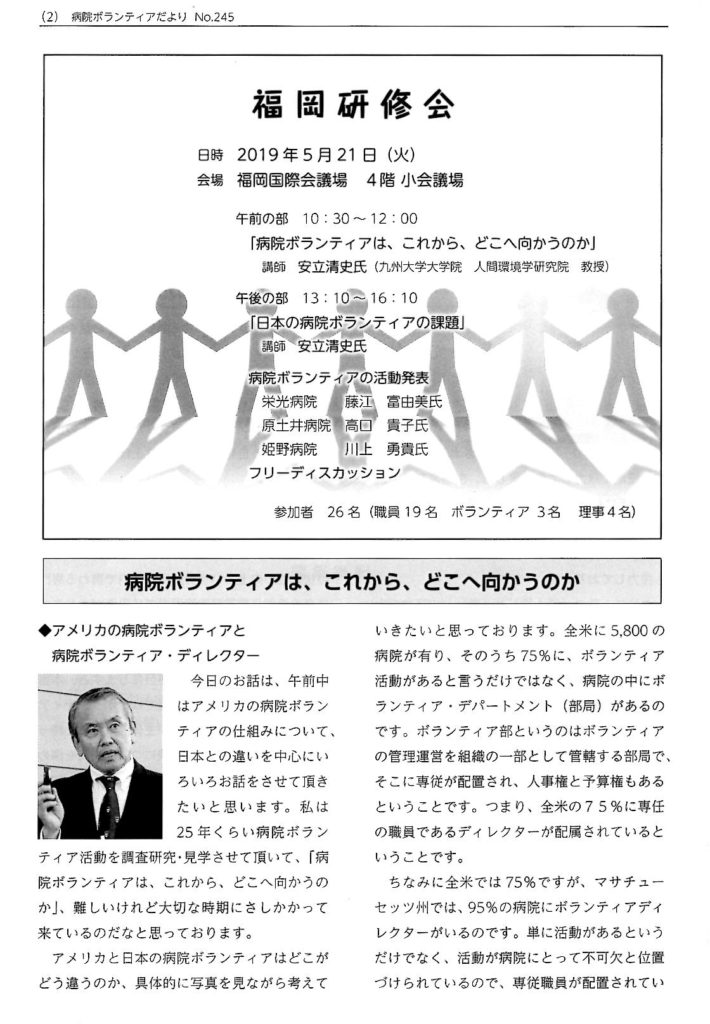参院選に向けていろいろな議論がなされています。大きな話題のひとつは、今回もまた投票率の最低を更新するのではないか、とくに若者の投票率がどこまで落ちるか、ということだと思います。選挙のたびに、ゼミや授業でもこの話題を、学生とディスカッションするのですが、意想外の答えが出てきたりして、なかなか面白いのです。大学1,2年生からは「感心がないわけではないが、何も知らない私たちが投票していいものか、責任感が重くて投票できない」など。これは意想外でしたね。
さて、その後「思考実験」をしてみたのです。「このまま順調に投票率が下がり続けると、最終的に、どこまで落ちるだろうか」「国政選挙なのだが、投票者ゼロということはありうるだろうか」「投票者がたった一人の場合でも、選挙というのは成立するだろうか」「投票率がどこまで下がると選挙の正統性が失われるだろうか」などなど。
かつて柄谷行人は「選挙などやめて、くじ引きにしたら良い」という大胆な提案をしていました。現状をみていると「選挙よりもくじ引きのほうが民意を反映する」という皮肉なパラドクスが、にわかに現実味を帯びてきたように思います。
「病院ボランティアだより」№245(2019年6月号)
日本病院ボランティア協会から「病院ボランティアだより」№245(2019年6月号)が送られてきました。この5月に私が福岡国際会議場で行った福岡研修会での講演が報じられています。なんと7ページにもわたって私の講演内容が詳細に掲載されています。当日のことが思い出されます。みなさん熱心に聞いて下さいました。詳細については、日本病院ボランティア協会のホームページからお問い合わせ下さい。
https://www.nhva.com/
うどん県香川の心に残るうどん店
この秋に香川の丸亀市にいくことになりました。そこで録画してあったNHK・BSプレミアムの「新日本風土記」の「うどん」という番組を観ました。中でも一番こころに残ったのが、多度津町の小さな小さなうどん店のこと(画面からは多奈加という店名が見えます)。だいぶ高齢のおじいさんとおばあさんが朝4時に仕込みをはじめて、地元の人むけに一日わずか30食ぶんしか作らないといううどん店です。お客さんは平均10人くらい、1食280円といいますから、これで生活できるのか心配になります。しかも高齢の常連さんは一杯を食べきれない。それを自宅まで届けています。これが香川うどんの心なんでしょうね。香川うどんのディープさを教えられました。
でも、こういうお店、いったい、どうやって見つけて取材したんでしょうか。「新日本風土記」は、地方局に配属された新人ディレクターの「卒論」みたいなものなのだと、制作統括の方がおっしゃっていました。数年間の赴任の間にあたためた企画や素材を、最後に「卒業制作」のようにして作り上げる。もちろ渋谷のNHKの地下に一週間くらい滞在して徹底して編集し、それを多くの関係者がコメントして作り込んでいく……なるほど、NHK地方局の底力すごいです。
黒澤明の「羅生門」を観る─夢幻能の世界
福岡市図書館シネラで黒澤明の『羅生門』を観ました。学生時代に一度観ているはずですから約40年ぶりの再見です。驚きました。あまりにも覚えていないことばかりだったので。なるほどこうだったのか。
事件の関係者3人が3様の「事実」をしゃべる──つまり3人の異なった殺人者が現れる、とくに3人目は巫女が出てきて死者を代弁する。これは夢幻能だ。そういえば竜安寺の石庭のようなところに関係者が並べられていて、あぁこの映画は能舞台なのだ、能仕立てだったのだ。
さらに多襄丸の三船は「七人の侍」の菊千代にそっくり、志村喬や千秋実、加東大介とともに「七人の侍」はもうここから始まっていたのだ。
結論。映画は一度観ただけでは分からない。本と同じように二度、三度と観るたびに違って見えてくる、違ったものが見えてくる。これって「羅生門」のメイン・メッセージだったんだな。
じつは芥川龍之介の原作にはない第4の視点として、最後に杣(そま)売りの志村喬も語るのです。でもこれで殺人者が4人になるわけではなく、また、この杣売りが、最後にどんでん返しのような形で、黒澤明的なヒューマニズムのオチをつけるところが、ちょっといまいちな気がします。
大阪で「介護保険と非営利組織はどこへ向かうか」というお話しをしました
「大阪市宅老所・グループハウス連絡会」から勉強会に呼んでいただき「介護保険と非営利組織はどこへ向かうか─福祉系NPOのこれから」というお話しをしました。G20大阪サミットと梅雨入りの大雨で交通の影響がありましたが、熱心な皆さんにお集まりいただきました。
当日の課題は、介護保険20年でなぜNPO法人がこんなにも苦境に立つようになってしまったのか、という疑問を解くことでした。
認定NPO法人・市民福祉団体全国協議会のホームページに掲載された私の論文「介護保険と非営利はどこへ向かうか」を踏まえてお話ししました。その原因のひとつは当初の制度設計にあるのではないか。営利と非営利の事業者を区別せずに混ぜてしまった疑似市場の仕組みの結果、行動経済学のいう「市場が道徳を締め出す」現象が起きているし、「ビッグデータ」を活用して超複雑怪奇なシミュレーションを駆使して介護報酬を微調整していく仕組み、その結果、巨大な中央管理システムが、営利でも非営利でもない「半営利」の仕組みを生み出していることなどを論じました。この結果、制度(というか財政)の持続可能性は高まるかもしれないが、介護保険が一種のブラックボックスのようになった結果、当初の目的だった「市民による福祉」、住民参加や市民参加による「市民福祉」や当事者のエンパワメントなどは、蜃気楼のように見えなくなってしまったのではないでしょうか。
このような現状にたいして、小竹雅子の『総介護社会』は、障がい者の自立生活運動をモデルに、上からの押しつけパターナリズムになりやすいサービスの現物給付だけでなく「現金給付」にこそ、利用者を当事者にしていくエンパワメントの可能性があると論じているのではないか。介護保険の「改正」につぐ改正で、住民参加・市民参加型らしさを脱色されてきた中で、行政や事業者の上からのパターナリズムを克服していくこと、利用者や消費者を当事者へと転換していくエンパワメント機能にこそ、NPOらしさがあるのではないか、などと論じました。
最後に、レスターM.サラモンの『NPOと公共サービス―政府と民間のパートナーシップ』を解読しながら、現状では、行政とNPOとが「二者関係」の中で、いつのまにか上下関係や支配・被支配関係になりがちだと説明しました。サラモンによれば、NPOが行政と対等になり得るのは「三者関係」の中においてのみだといいます。アメリカの福祉システムの特徴は、行政とNPOの関係が「二者関係」ではなく、両者の上に「第三者」が存在することです。それこそ「第三者による政府」です。これは行政とNPOとが、ともに立場をこえて、互いが一種のバーチャルな存在となって「第三者による政府」を作るということです。つまり現実の上に「バーチャルな福祉システム」をつくるところにポイントがあります。バーチャルな関係ですから不安定ですが「二者関係」を超えた「三者関係」が生み出せないと、かならず行政によるNPO支配が始まることになると言います。対決や対立でなく、協力・協働するということは、このバーチャルな新しい関係を作ることだと言います。コトバの上だけではなく、半実体となった協力関係が作れるかどうか、それこそが非営利組織がこの世界に根づいて、社会を変えていくことなのではないか。そういうことをお話ししました。
インフォメーション
安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照


カウンタ
- 396215総訪問者数:
- 16今日の訪問者数:
- 33昨日の訪問者数:
最近の記事
- 唐津小旅行
- 梅雨明けの虹でしょうか
- 福岡の「第二宅老所よりあい」
- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評
- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました
- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評
- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)
- ジャカランダの花
- 図書館奇譚
- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します
- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました
- 長湯温泉(その2)
- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)
- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します
- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉
- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る
- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉
- 「無法松の一生」を観る
- 大濠雲海
- 博多で講演と対談をしました
- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました
- Chat GPTに論争をふっかける
- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎
- 福岡の桜、一挙に満開
- 福岡の桜開花(3/27)
- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます
- 福岡城跡の仮設・天守台
- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー
- 福岡・桜祭り
- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催
- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催
- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告
- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問
- 認定NPO法人・市民協の理事会
- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行
- ボストン・シンフォニーの小澤征璽
- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒
- 加藤周一、座頭市を語る
- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史
- ジブリ・加藤周一・座頭市
- 立命館大学・加藤周一文庫のこと
- 加藤周一の小さな机
- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」
- 私の原点──加藤周一その2
- 私の原点──加藤周一
- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード
- 名古屋のジブリパークに行きました
- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました
- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します
- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと
- マンガ版「君たちはどう生きるか」
- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集
- 「君たちはどう生きるか」という問い
- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです
- 戦争の時代に宮崎アニメを読む
- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験
- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます
- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします
- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました
- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました
- 社会学、出会い直しの会
- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載
- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号
- 市民協ミーティング2023 in 佐賀
- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン
- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました
- 『福祉社会学研究』№20 での書評
- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム
- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました
- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています
- ブックトーク後のサイン会
- 新著『福祉の起原』のブックトーク
- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート
- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション
- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載
- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」
- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去
- 超高齢社会に社会学からの解
- 九州大学からの海外発信
- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。
- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』
- 最終講義日程(九州大学広報室)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました
- 新年のご挨拶
- 見田宗介先生を偲ぶ会
- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)
- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える
- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)
- 大阪・中之島の「大阪図書館」
- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします
- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」
- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました
- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)
- 名画座の打率
- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』
アーカイブ
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2009年8月
- 2008年10月
- 2008年8月
- 2006年8月
- 2005年8月
- 2004年8月
Count per Day
- 482874総閲覧数:
- 57今日の閲覧数:
- 409昨日の閲覧数:
- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)
- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて
- 梅雨明けの虹でしょうか
- 小林秀雄の「山の上の家」
- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家
- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん
- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会
- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画
- 周防大島の上空
- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く
- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん
- 著書・論文・報告書など
- 唐津小旅行
- 首里のあひる
- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く
- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」
- ベンツ6
- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場
- 博多・灯明ウォッチングが始まります
- 今週の一押しポッドキャスト
カテゴリー
- トップ (1,659)