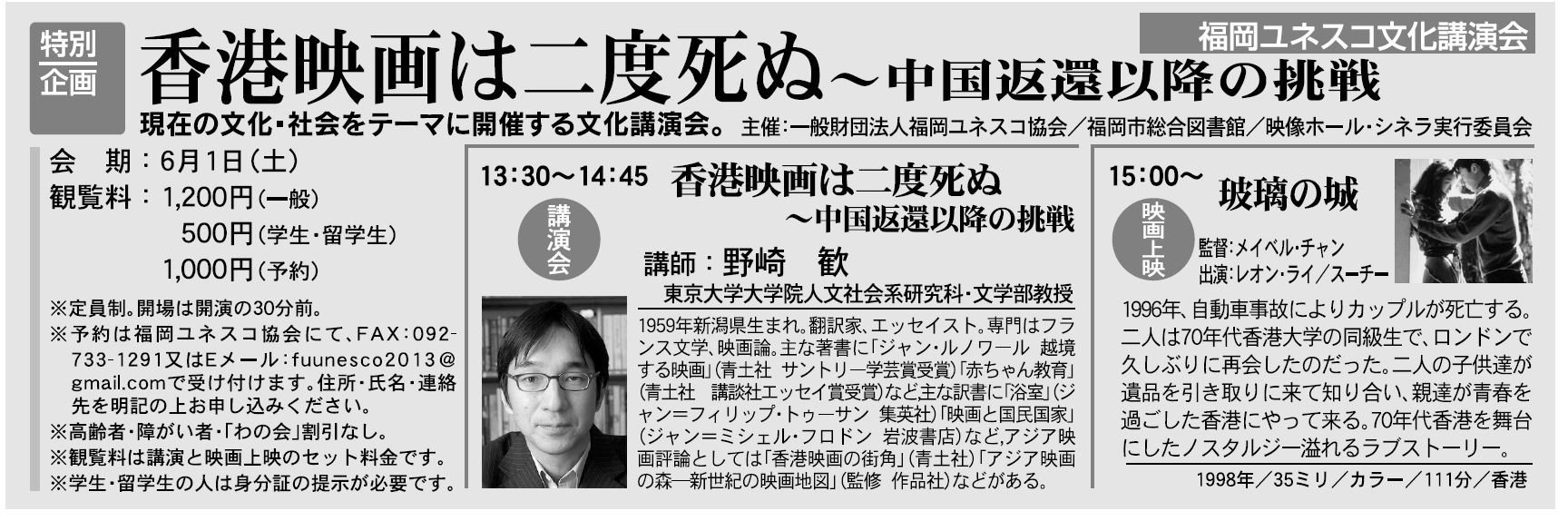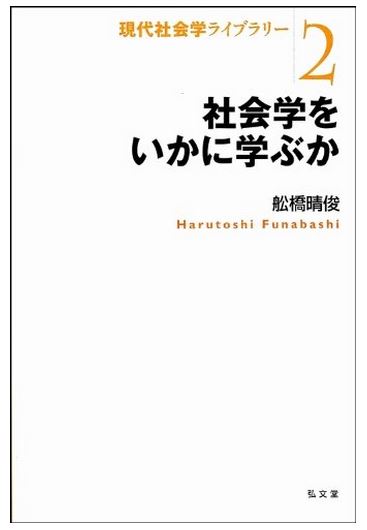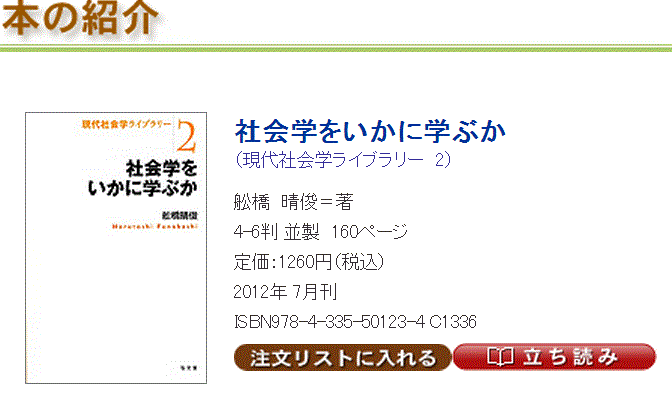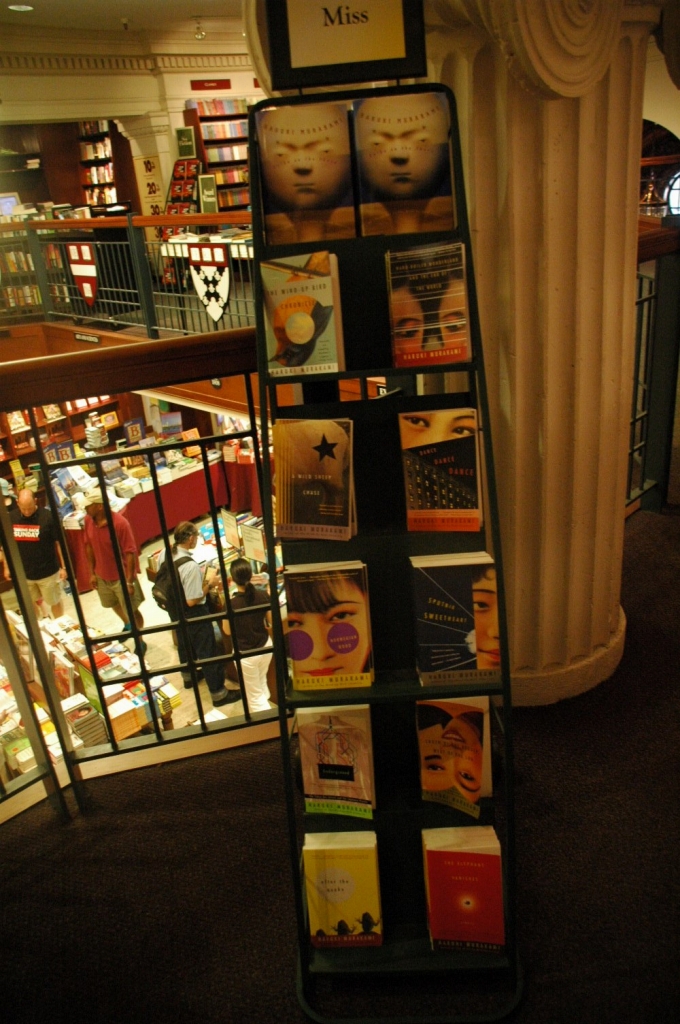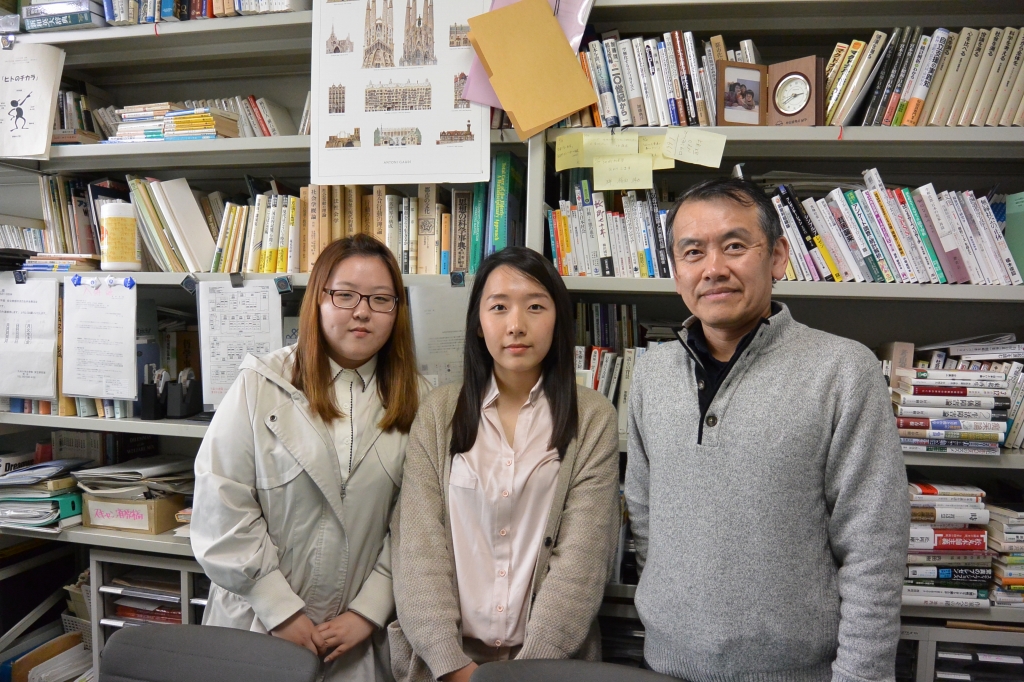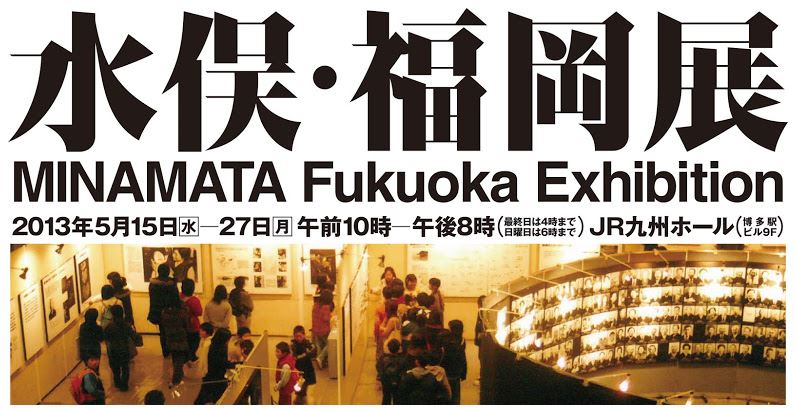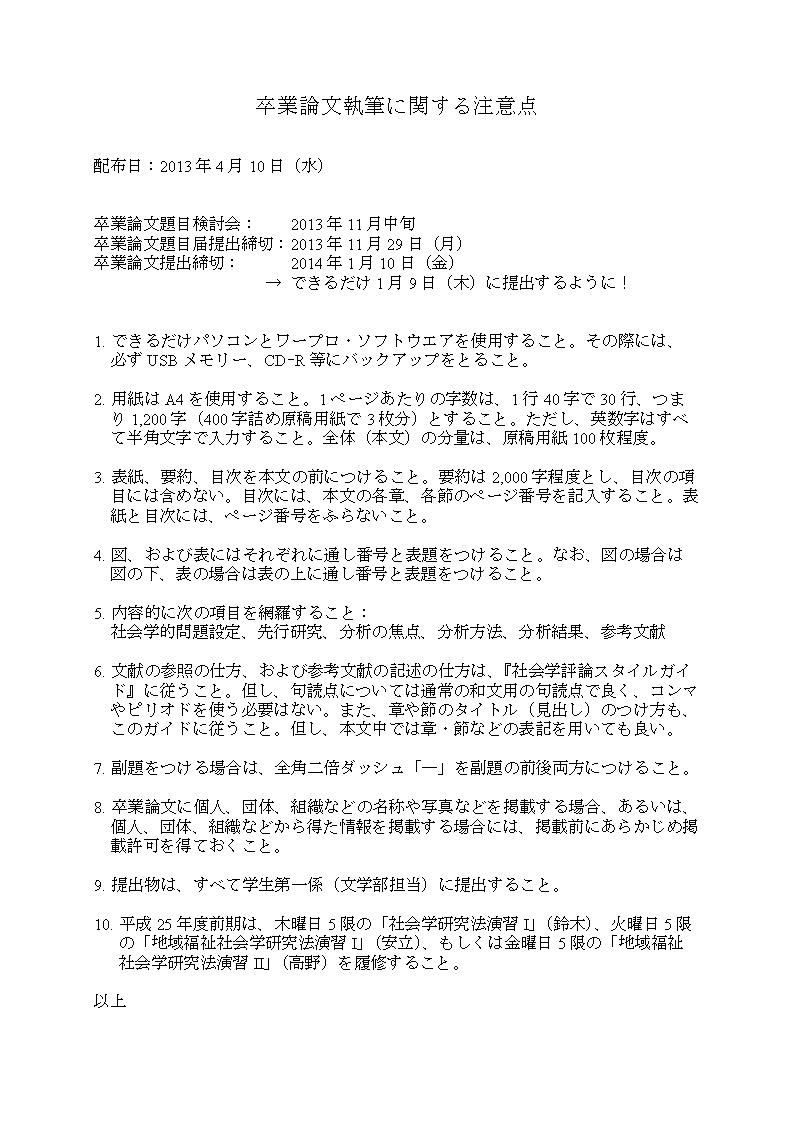社会学演習 2013年4月25日
社会学演習
2013年04月25日
【ラジオ版学問ノススメ】
http://www.jfn.co.jp/susume/
*沢木耕太郎
http://podbay.fm/show/216964966/e/1303174800
*大江健三郎
http://podbay.fm/show/216964966/e/1346115480
English as a Second Language Podcast
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
【幻想図書館】
ボストン
http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/BPL/Night_Library.html
ニューヨーク
http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/NYPL/NYPL.html
【社会学者・大澤真幸の書評】
http://book.asahi.com/ebook/master/1177/index.html
【社会学者・小熊英二】
http://oguma.sfc.keio.ac.jp/chosaku.html
【内田樹のブログ】
http://blog.tatsuru.com/
石牟礼道子さん、最後の水俣病記念講演会
水俣病記念講演会
水俣病記念講演会に参加してきました。社会学の院生や学生も何人か参加していたようです。(・・・こう書き写してみると、あらためて、すごい意味深な表題ですね。ふつう「記念」というと、いいことを記念して・・・ということになるんだと思うんですけどね。おそらく忘れないように風化しないように「記念」して考え続けましょう、ということなのでしょうが・・・)。
680席と言われていたのに、満員のうえ立ち見もでる大盛況ぶりでした。すごいですね。みんな入場の時から殺気だっていましたよ。
池澤夏樹さん、柳田邦男さんなど有名人が話す4時間近くにおよぶ大講演会。その最後のとりをつとめられたのが石牟礼道子さんでした。パーキンソン病のため、今回が講演会などで人前にでる最後の機会だとのことでした。内容も、まるで、遺言のような、遺書のような・・・みんな、しーんと静まりかえって聞いておりました。
http://www.youtube.com/watch?v=VvcoFlXTYro
『社会学をいかに学ぶか』(舩橋晴俊著,弘文堂)
舩橋晴俊著『社会学をいかに学ぶか』(弘文堂)
この書は、たんなる社会学入門書ではない。社会学の学び方を切り口として、「学問的空振り」という、きわめて重要かつ本質的な問題提起を行っている。
私たちは、「人生の空振り」をしているのではないか、と問いかけているのだ。
この問いに、どきり、としない人はいるだろうか。
2年生の授業で、問いかけてみた。
ほぼ全員が、空振りしているかもしれない、と答えた。
私だって問いかけられたら、空振りの人生だった、と答えるかもしれない。
これは、重大事だ。たいへんだ。
大学で学ぶこと意味や異議が根本的に問われている。
*
「空振り」とは何か。
やる気があり、努力しているにもかかわらず、手応えがつかめない。学んだことの実感がなく、通り過ぎていくような気がする。何か大切なものを獲得しり、達成した感じがしない。何か虚しく空をつかんでいるような感じだ。やっていることの本当の意味や意義が感じられない・・・
そういうことだろう。
「努力しているにもかかかわらず」というのがポイントだ。
もともとやる気のない人、努力していない人は、バットを振っていないのだから、当たるはずもないし、したがって、空振り、もあり得ない。
ここでは、そういう人のことは、考えない。
問題は、やる気があって、努力しているにもかかわらず、だ。
典型例を出してみよう(特定の具体的な個人ではありません、念のため。集合的なケースを抽象化したものです)。
成績優秀、やる気も十分、授業には皆勤。それどころか、朝の1限から5限まで、毎日出席。
3年生からは、夜の公務員講座まででている。
学芸員資格、教員免許、社会調査士など、資格もたくさんとっている。
でも、卒論になったとたん、まるで書けない。
テーマがまるでない、のだ。自分が何を本当にやりたいのか、分からない。
卒論に取り組もうにも、取り組みたいテーマが見つからない、と暗い顔をしている。
書けない、どうしよう、混乱する。11月になって昼間が短くなると、夕方、不安になるのだろう、書けません、と相談にやってきて、やがて涙目になる・・・
こういう「優等生」は、珍しいことではない。
典型的な「空振り」なのだ。
4年間、まじめに熱心に「学んだ」。
しかしそれは受動的に教えられることを吸収しただけ。
喩えていえば、教室という画面で放映されているTV番組のようなものを、ただひたすら、まじめに見てきた、ということ。
教科書も読んできた。黒板の板書もノートした。でも、それは、自分で見つけて読みたいと思って読んだわけではなく、受動的に薦められたり、教科書だったから、読んだだけ。読んで、それで、おしまい。
就活も、勉強すれば確実に点がとれて合格しそうな公務員試験を、受験勉強と同じくひたすら地道に忍耐強くこなしただけ。
公務員になって、何か、やりたいことや、実現したい夢があるわけではない。
(公務員受験が悪いわけではありません。公務員試験にまっしぐらな人に、ありがちなので、ひとつの事例として取り上げているだけ。公務員を一般企業に置き換えても当てはまることは、すぐに分かるでしょう)
そういう「優等生」が、卒業を目前にして陥る激しい「空振り」感。
昔だったら、ここで一念発起、留年して世界放浪、自分探しの旅、となるのだろうが・・・(作家の沢木耕太郎や、写真家の藤原新也、などがその典型。沢木耕太郎の『深夜特急』、藤原新也の『全東洋街道』などは、いまでも胸を熱くする青春の書として、お薦めだ。)。
でも今では、そんな泥臭いことはやらない。
自分の空振り感は、封印して、まぁ、こんなものかな、と見切って、さっさと就職していく。
卒業時に「社会学って、何でも出来るというので進学しましたが、結局、どんなものかよく分かりませんでした」とか言って卒業していく。
うーん、こまったなぁ。
*
こういう学生を、私たち教員も、毎年、数限りなく見てきた。
社会学研究室が楽しいのは、それはそれでけっこうなんだけど、社会学そのものの魅力が分からないまま卒業していくのなら、われわれはいったい何をしておるのか、ということになってしまう。
学生がバッターボックスで「空振り」しているのを見ている私たち教員は、さしづめ無力な「コーチ」とか無能な「監督」にあたる。
期待して打席に送り出したバッターたちが、ぜんぜんヒットを打てず、三振の山を築いていく・・・今年も完封負けか、などというのは、じつに、残念な気持ちなのだ。
「監督失格」として、更迭されそうな気がする。
*
このままではいかん。
と、今年は、船橋晴俊さんの『社会学をいかに学ぶか』を教科書にして、2年生からいっしょに空振りをしない方向を模索しようと考えた。「社会学」とあるが、社会学の話だけではない。私たちすべてに共通している課題なのだと思う。
社会調査実習を受講している3年生は、こちら。
ボストン・マラソン爆弾テロ事件
ボストン・マラソン爆弾テロ事件
昨日、村上春樹のボストンを歩く、というページを紹介して、さて、次はボストン・マラソンか、と思っていたやさき、ボストン・マラソンをねらった爆弾テロ事件が勃発しました。ショックですね。
今回のボストン・マラソン爆弾事件の現場は、ボストン・マラソンのフィニッシュ地点のようです。それはまさにボストン・パブリック・ライブラリ(ボストン公共図書館)の真ん前なんです。この図書館については、旧ホームページに写真入りの「幻想図書館」として紹介していますが、じつに素晴らしいところなのです・・・。
http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~adachi/Library/BPL/Night_Library.html
村上春樹のボストンを歩く
村上春樹のボストンを歩く
「東京紅團」という作家や文学作品の現場を訪問・紹介するというかなりマニアックなサイトがあって、ひそかに愛読しているんですが、今週「村上春樹のボストンを歩く」というのが出ました。村上春樹ファンは多いことと思います。私も8年くらい前、ボストンに住んでいたとき、村上春樹が通いつめたという中古レコード店にも行ったことがあります。
また、ハーバード大学だ開催された日本文学のシンポジウムに参加したあとで、村上春樹さん本人に、お会いしたこともあるんです。
http://www.tokyo-kurenaidan.com/haruki_boston_1.htm
「水俣・福岡展」が開催されます。石牟礼道子さん、柳田邦男さん、池澤夏樹さんも来られます。
私の所属する九州大学大学院人間環境学研究院も協賛して「水俣・福岡展」が開催されます。なんと4月21日の「水俣病記念講演会」(JR九州ホール)には、現在、ご病気療養中の石牟礼道子さんも登場されるようです。さらにノンフィクション作家の柳田邦男さん、作家の池澤夏樹さんなど、そうそうたる面々。これは何をおいても駆けつけなければ。
http://minamata-fukuoka.blogspot.jp/
きょうは九州大学の入学式
きょうは九州大学の入学式です。
大学全体の入学式は、巨大すぎるので、出席したことがなかったのですが、こんなこともやっているんですね。
http://www.youtube.com/watch?v=48_C7gGsQvo
卒論が始まります
卒論が始まります
今年も5名の4年生の卒論指導を受け持つことになりました。
でも、ここ数年、就活状況が厳しいようで、なかなか卒論のほうに心も身体も向かわない(向けることができない)ようです。卒論に着手できるのはよくて6月、ひどい場合には9月中旬、いや11月まで就活がつづく(そのうえ決まらない)ようなこともおこっています。なんだか就活で大学の4年間がめちゃめちゃにされているような・・・。
http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/socio/news/2013410.html
インフォメーション
安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照


カウンタ
- 392326総訪問者数:
- 19今日の訪問者数:
- 27昨日の訪問者数:
最近の記事
- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る
- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉
- 「無法松の一生」を観る
- 大濠雲海
- 博多で講演と対談をしました
- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました
- Chat GPTに論争をふっかける
- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎
- 福岡の桜、一挙に満開
- 福岡の桜開花(3/27)
- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます
- 福岡城跡の仮設・天守台
- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー
- 福岡・桜祭り
- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催
- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催
- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告
- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問
- 認定NPO法人・市民協の理事会
- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行
- ボストン・シンフォニーの小澤征璽
- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒
- 加藤周一、座頭市を語る
- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史
- ジブリ・加藤周一・座頭市
- 立命館大学・加藤周一文庫のこと
- 加藤周一の小さな机
- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」
- 私の原点──加藤周一その2
- 私の原点──加藤周一
- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード
- 名古屋のジブリパークに行きました
- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました
- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します
- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと
- マンガ版「君たちはどう生きるか」
- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集
- 「君たちはどう生きるか」という問い
- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです
- 戦争の時代に宮崎アニメを読む
- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験
- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます
- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします
- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました
- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました
- 社会学、出会い直しの会
- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載
- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号
- 市民協ミーティング2023 in 佐賀
- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン
- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました
- 『福祉社会学研究』№20 での書評
- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム
- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました
- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています
- ブックトーク後のサイン会
- 新著『福祉の起原』のブックトーク
- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート
- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション
- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載
- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」
- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去
- 超高齢社会に社会学からの解
- 九州大学からの海外発信
- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。
- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』
- 最終講義日程(九州大学広報室)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました
- 新年のご挨拶
- 見田宗介先生を偲ぶ会
- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)
- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える
- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)
- 大阪・中之島の「大阪図書館」
- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします
- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」
- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました
- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)
- 名画座の打率
- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』
- 中井久夫さん追悼
- 見田宗介先生追悼─『社会学評論』№289編集後記
- 「ふたりのウルトラマン」とは何か
- 「ゴルバチョフ:老政治家の遺言」を観ました
- オンラインでの社会調査実習
- 村上春樹ライブラリーのジャズ
- 西日本社会学会年報に私の書評が掲載されました
- 西日本社会学会年報2022に、拙著『超高齢社会の乗り越え方』の書評が掲載されました
- 見田宗介先生、最後の年賀状
- 社会学者の見田宗介先生が亡くなられました
- NHK/IPC 国際共同制作「映像記録 東京2020パラリンピック」を見ました
- 「no art, no life」と「ツナガル・アートフェスティバル福岡」
- 九州大学文学部の卒業式
- 感慨も湧かないのか、かえって感慨深いのか──いよいよ卒業式です
- no art, no life 〜表現者たちの幻想曲
- 東京大学社会学の佐藤健二さんの最終講義
アーカイブ
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2009年8月
- 2008年10月
- 2008年8月
- 2006年8月
- 2005年8月
- 2004年8月
Count per Day
- 471953総閲覧数:
- 26今日の閲覧数:
- 88昨日の閲覧数:
- まさかのどしゃぶりの雨の中の柳川川下り
- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて
- 小林秀雄の「山の上の家」
- 「君たちはどう生きるか」──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉
- 松茸、有マス
- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画
- プロフィール
- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)
- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん
- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る
- 「無法松の一生」を観る
- 建築における人間工学はどうなっているのか
- かふか2
- 京都の漬物
- 宮澤賢治の「圖書館幻想」(ダルゲとダルケ)
- 「讃岐・超ディープうどん紀行」(村上春樹)を追いかける
- 映画「ローザ・ルクセンブルク」を観ました
- 夢の本屋紀行─中国・南京の先鋒書店
- 「なめとこ山の熊」鉛温泉・藤三旅館
- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家
カテゴリー
- トップ (1,643)