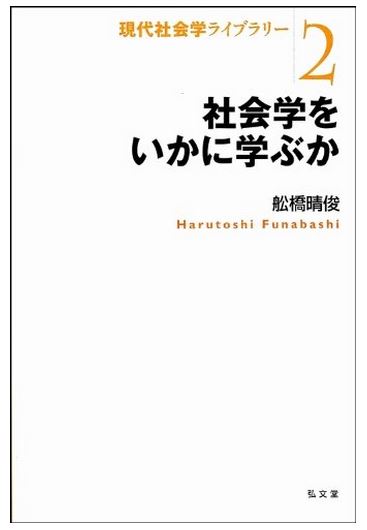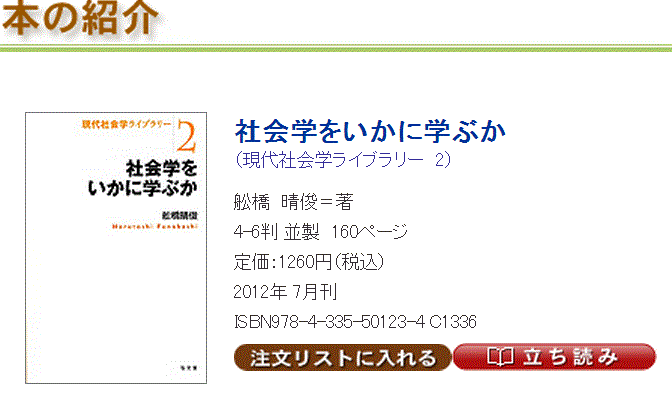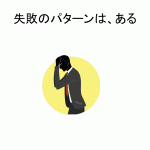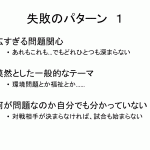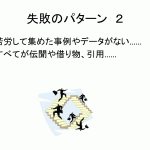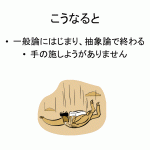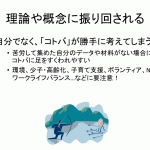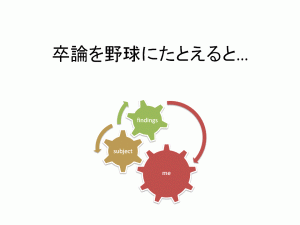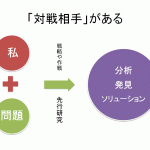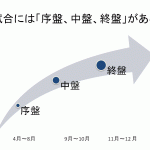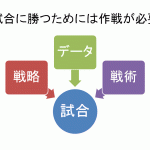卒論提出日に思う
きょうは4年生の卒論提出日です。九州大学社会学では学部4年生の卒論に課される字数が多いので(4万字、ということは400字の原稿用紙換算で100枚程度)、学生たちも悪戦苦闘しているようです。
卒論指導をしていて感じることがありました。
それは学生が「書く」のではなく「打つ」ようになってきていることです。しかもパソコンのキーボードでなく、どうやらスマホに打っているようなのです。スマホの画面で「打つ」、というよりは「さわっている」「フリックしている」というべきでしょうか。授業中でもノートを広げている学生が少なくなりました。
おいおい、それって、「書く」ことなのかなぁ、という思いを禁じ得ないのです。
「書く」ってのは、頭で考えたことを、指先が筆記していくあいだに、あっ、これは違うなとか、これは平凡すぎるのなぁとか、こりゃつまらないやとか、自分の考えたことにたいして、指先が批評したり批判したり反抗していったりすることの経験でもあるわけです。
筆記しながら、指先やペン先が、頭の意図と違うことを書き始めたり、コトバが不思議と踊り出して、コトバあそびが始まったり、あらぬことを主張しだしたり・・・ようするに、考えたことと、書かれたこととが、ずれてきたりして、それがまた、新しい発見になったり、文章の起爆剤になったりするものだと思うのです。
・・・とここまで書いてきて、いかん、これは「deja vu」(既視感)だと思いました。30年前に、私たちが、上の世代から浴びせられた違和感。「君たち、手紙はワープロで書いてはいかん」とか、「ワープロになったら文体が変わった」とか言われた経験。
ふうん、なるほどねぇ、これが時代の移り変わりというものか。
かつて、私たちが、パソコンを使い出した時に上の世代が感じた違和感を、いま、私たちが下の世代にたいして感じているわけなんだなぁ。
でも、このところ、手書きが、やっぱりいい、と思うようになりました。手書きの時に、いちばん充実して考えることができるような気がする。手書きしながら、頭でなく指先が考え出す時が、いちばん、おもしろくたのしいアイデアが膨らんでいる。そう思うようになりました。とくに早朝におきて、布団のなかで、ぬくぬくしながら、小さなメモ帳に縦書きで着想を書いているときなんかに、それを強く感じますね。
不安な時代なのか、初詣の人手が例年以上に多かった・・・
『社会学をいかに学ぶか』(舩橋晴俊著,弘文堂)
舩橋晴俊著『社会学をいかに学ぶか』(弘文堂)
この書は、たんなる社会学入門書ではない。社会学の学び方を切り口として、「学問的空振り」という、きわめて重要かつ本質的な問題提起を行っている。
私たちは、「人生の空振り」をしているのではないか、と問いかけているのだ。
この問いに、どきり、としない人はいるだろうか。
2年生の授業で、問いかけてみた。
ほぼ全員が、空振りしているかもしれない、と答えた。
私だって問いかけられたら、空振りの人生だった、と答えるかもしれない。
これは、重大事だ。たいへんだ。
大学で学ぶこと意味や異議が根本的に問われている。
*
「空振り」とは何か。
やる気があり、努力しているにもかかわらず、手応えがつかめない。学んだことの実感がなく、通り過ぎていくような気がする。何か大切なものを獲得しり、達成した感じがしない。何か虚しく空をつかんでいるような感じだ。やっていることの本当の意味や意義が感じられない・・・
そういうことだろう。
「努力しているにもかかかわらず」というのがポイントだ。
もともとやる気のない人、努力していない人は、バットを振っていないのだから、当たるはずもないし、したがって、空振り、もあり得ない。
ここでは、そういう人のことは、考えない。
問題は、やる気があって、努力しているにもかかわらず、だ。
典型例を出してみよう(特定の具体的な個人ではありません、念のため。集合的なケースを抽象化したものです)。
成績優秀、やる気も十分、授業には皆勤。それどころか、朝の1限から5限まで、毎日出席。
3年生からは、夜の公務員講座まででている。
学芸員資格、教員免許、社会調査士など、資格もたくさんとっている。
でも、卒論になったとたん、まるで書けない。
テーマがまるでない、のだ。自分が何を本当にやりたいのか、分からない。
卒論に取り組もうにも、取り組みたいテーマが見つからない、と暗い顔をしている。
書けない、どうしよう、混乱する。11月になって昼間が短くなると、夕方、不安になるのだろう、書けません、と相談にやってきて、やがて涙目になる・・・
こういう「優等生」は、珍しいことではない。
典型的な「空振り」なのだ。
4年間、まじめに熱心に「学んだ」。
しかしそれは受動的に教えられることを吸収しただけ。
喩えていえば、教室という画面で放映されているTV番組のようなものを、ただひたすら、まじめに見てきた、ということ。
教科書も読んできた。黒板の板書もノートした。でも、それは、自分で見つけて読みたいと思って読んだわけではなく、受動的に薦められたり、教科書だったから、読んだだけ。読んで、それで、おしまい。
就活も、勉強すれば確実に点がとれて合格しそうな公務員試験を、受験勉強と同じくひたすら地道に忍耐強くこなしただけ。
公務員になって、何か、やりたいことや、実現したい夢があるわけではない。
(公務員受験が悪いわけではありません。公務員試験にまっしぐらな人に、ありがちなので、ひとつの事例として取り上げているだけ。公務員を一般企業に置き換えても当てはまることは、すぐに分かるでしょう)
そういう「優等生」が、卒業を目前にして陥る激しい「空振り」感。
昔だったら、ここで一念発起、留年して世界放浪、自分探しの旅、となるのだろうが・・・(作家の沢木耕太郎や、写真家の藤原新也、などがその典型。沢木耕太郎の『深夜特急』、藤原新也の『全東洋街道』などは、いまでも胸を熱くする青春の書として、お薦めだ。)。
でも今では、そんな泥臭いことはやらない。
自分の空振り感は、封印して、まぁ、こんなものかな、と見切って、さっさと就職していく。
卒業時に「社会学って、何でも出来るというので進学しましたが、結局、どんなものかよく分かりませんでした」とか言って卒業していく。
うーん、こまったなぁ。
*
こういう学生を、私たち教員も、毎年、数限りなく見てきた。
社会学研究室が楽しいのは、それはそれでけっこうなんだけど、社会学そのものの魅力が分からないまま卒業していくのなら、われわれはいったい何をしておるのか、ということになってしまう。
学生がバッターボックスで「空振り」しているのを見ている私たち教員は、さしづめ無力な「コーチ」とか無能な「監督」にあたる。
期待して打席に送り出したバッターたちが、ぜんぜんヒットを打てず、三振の山を築いていく・・・今年も完封負けか、などというのは、じつに、残念な気持ちなのだ。
「監督失格」として、更迭されそうな気がする。
*
このままではいかん。
と、今年は、船橋晴俊さんの『社会学をいかに学ぶか』を教科書にして、2年生からいっしょに空振りをしない方向を模索しようと考えた。「社会学」とあるが、社会学の話だけではない。私たちすべてに共通している課題なのだと思う。
社会調査実習を受講している3年生は、こちら。
梅棹忠夫の『知的生産の技術』
梅棹忠夫の『知的生産の技術』
とうとうこういう時代になったのだ。
きょう、社会調査実習に関する授業の中で、私にとってはサプライズがあった。
梅棹忠夫の『知的生産の技術』(岩波新書)の紹介をしたら、誰ひとり、読んだことのある学生がいなかった。大学院生のティーチング・アシスタントですら、読んだことも聞いたこともないという。
があーん。そういう時代になったのかなぁ。そういえば、村上春樹も、みんな、読んだことがないと言っていたし。
でもなぁ、35年くらい前、私が高校生だった頃は、みんな高校生で、この本は読んでいたぞ・・・てなことを言っても、まったくの「おじさん言説」になってしまう今日このごろ、秋の夕暮れであった。
さて、この流れは、どこまでいくのか。
卒業論文執筆に関する注意点
卒業論文執筆に関する注意点
第一回中間報告(20 枚程度)締切:2011 年7 月末日
第二回中間報告(40 枚程度)締切:2011 年9 月末日(なお、分量は400 字詰め原稿用紙換算での枚数)
卒業論文題目検討会: 2011 年11 月中旬
卒業論文題目届提出締切:2011年11 月30 日
卒業論文提出締切: 2012 年1月10日 午後5時締め切り
→ できるだけ前日までに提出するように!
1. パソコンとワープロ・ソフトウエアを使用し、必ずUSB メモリー、CD-R 等にバックアップをとること。
2. 用紙はA4 を使用すること。1 ページあたりの字数は、1 行40 字で30 行、つまり1,200 字(400 字詰め原稿用紙で3 枚分)とすること。ただし、英数字はすべて半角文字で入力すること。全体(本文)の分量は、原稿用紙100 枚程度。
3. 表紙、要約、目次を本文の前につけること。要約は2,000 字程度とし、目次の項目には含めない。目次には、本文の各章、各節のページ番号を記入すること。表紙と目次には、ページ番号をふらないこと。
4. 図、および表にはそれぞれに通し番号と表題をつけること。なお、図の場合は図の下、表の場合は表の上に通し番号と表題をつけること。
5. 内容的に次の項目を網羅すること:社会学的な問題設定、先行研究のレビュー、分析の焦点、分析方法、分析結果、まとめと考察、参考文献
6. 文献の参照の仕方、および参考文献の記述の仕方は、『社会学評論スタイルガイド』に従うこと。但し、句読点については通常の和文用の句読点で良く、コンマやピリオドを使う必要はない。
7. 提出物は、すべて学生第一係(文学部担当)に提出すること。
8. 質問等がある場合には個別に担当教員に連絡すること。
9. 平成24年度前期は、火曜日 5 限の「社会学研究法演習I」を履修すること。
10.「社会学研究法演習I」の単位認定、成績判定は、上記2 回の中間報告に基づいて行う。
インフォメーション
安立清史(「超高齢社会研究所」代表、九州大学名誉教授)のホームページとブログです──新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。これまで『超高齢社会の乗り越え方』、『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』、『ボランティアと有償ボランティア』(弦書房)、『福祉NPOの社会学』(東京大学出版会)などの著書があります。「超高齢社会研究所」代表をつとめています。https://aging-society.jp/ 参照


カウンタ
- 396214総訪問者数:
- 15今日の訪問者数:
- 33昨日の訪問者数:
最近の記事
- 唐津小旅行
- 梅雨明けの虹でしょうか
- 福岡の「第二宅老所よりあい」
- 『福祉社会学の思考』(弦書房)の書評
- 「CareTEX福岡‘24」で講演をしました
- 共同通信 の『福祉社会学の思考』書評
- 中日新聞にコメントが掲載されました(東京新聞、北陸中日新聞にも)
- ジャカランダの花
- 図書館奇譚
- 【CareTEX福岡’24】の専門セミナーに登壇します
- 『ボランティアと有償ボランティア』が入試問題に出題されました
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が新聞で書評されました
- 長湯温泉(その2)
- ラムネ温泉(大分県竹田市・長湯温泉)
- CareTEX福岡’24 (マリンメッセ福岡)専門セミナーで講演します
- ジブリ温泉(その2)岩手県花巻温泉
- 映画「二十四の瞳」(木下恵介監督,1954)を観る
- ジブリ温泉(その1)──宮崎駿さんたちジブリのスタッフが制作途中に訪れた温泉
- 「無法松の一生」を観る
- 大濠雲海
- 博多で講演と対談をしました
- 新著『福祉社会学の思考』が出版されました
- Chat GPTに論争をふっかける
- 遣唐使や遣隋使の出航した荒津の崎
- 福岡の桜、一挙に満開
- 福岡の桜開花(3/27)
- 安立清史の新著『福祉社会学の思考』(弦書房)が出版されます
- 福岡城跡の仮設・天守台
- 中島岳志さんと國分功一郎さんの福岡ユネスコ文化セミナー
- 福岡・桜祭り
- 福岡ユネスコ文化セミナーの開催
- 福岡市でACAP(Active Aging Consortium in Asia Pacific)セミナー開催
- バルセロナ郊外─モンセラート僧院とパラドール・カルドナの一夜
- 新著『福祉社会学の思考』(弦書房)の予告
- 「かまきん(鎌倉文華館)」訪問
- 認定NPO法人・市民協の理事会
- チャン・ドンゴンと行く 世界「夢の本屋」紀行
- ボストン・シンフォニーの小澤征璽
- イタリア・ネオレアリズモ映画を観る──無防備都市と自転車泥棒
- 加藤周一、座頭市を語る
- 新年のご挨拶──「超高齢社会研究所」代表・安立清史
- ジブリ・加藤周一・座頭市
- 立命館大学・加藤周一文庫のこと
- 加藤周一の小さな机
- ジブリと加藤周一と「日本その心とかたち」
- 私の原点──加藤周一その2
- 私の原点──加藤周一
- 『ジブリと宮崎駿の2399日』驚きのエピソード
- 名古屋のジブリパークに行きました
- 愛知県社会福祉会館(名古屋市)で講演をしました
- 「住民参加型在宅福祉サービス団体研修会」(名古屋市)で講演します
- 沢木耕太郎の新著『夢ノ町本通り』のこと
- マンガ版「君たちはどう生きるか」
- 『熱風』の「君たちはどう生きるか」特集
- 「君たちはどう生きるか」という問い
- 「君たちはどう生きるか」もうすぐフランスでも公開だそうです
- 戦争の時代に宮崎アニメを読む
- プラネタリウムで「銀河鉄道の夜」体験
- 12月に愛知県名古屋市でセミナー講師をつとめます
- 中村学園大学で「社会福祉とボランティア」の授業をします
- 「記者ありき─六鼓・菊竹淳」を観ました
- 西日本新聞で『福祉の起原』が紹介されました
- 社会学、出会い直しの会
- 『福祉社会学研究』に私の著書『21世紀の《想像の共同体》─ボランティアの原理 非営利の可能性』の書評が掲載
- 『共生社会学』Vol.12──退任記念号
- 市民協ミーティング2023 in 佐賀
- 8月、市民協が佐賀・熊本・鹿児島でフォーラム・キャラバン
- 「鈴木敏夫とジブリ展」に行きました
- 『福祉社会学研究』№20 での書評
- 京都の同志社大学で「福祉社会学会」設立20周年シンポジウム
- 大阪ボランティア協会の早瀬昇さんが『ボランティアと有償ボランティア』を書評して下さいました
- 『放送レポート』最新号で『福祉の起原』が紹介されています
- ブックトーク後のサイン会
- 新著『福祉の起原』のブックトーク
- 不思議なシンクロ──「鈴木敏夫とジブリ展」がスタート
- 『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生 トークセッション
- 『社会学評論』最新号に『ボランティアと有償ボランティア』の書評が掲載
- シンポジウム「見田宗介/真木悠介を継承する」
- UCLAのスティーブン・ウォーレス教授の逝去
- 超高齢社会に社会学からの解
- 九州大学からの海外発信
- 九州大学での最終講義を行いました(2023年2月6日)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)が出版されました。
- 研究の国際発信──『超高齢社会の乗り越え方』
- 最終講義日程(九州大学広報室)
- 新著『福祉の起原』(弦書房)のカバーが決まりました
- 新年のご挨拶
- 見田宗介先生を偲ぶ会
- 戦争の乗り越えは可能か(西日本新聞・随筆喫茶)
- 「戦争の乗り越えは可能か」─「千と千尋の神隠し」から考える
- 佐藤忠男さんを偲んで(シネラ)
- 大阪・中之島の「大阪図書館」
- 北九州市立美術館の「祈り・藤原新也」
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』─香川県丸亀市でお話しをします
- 「コロナ禍のもとでのボランティアやNPO法人の活動の実態と課題──オンラインによる社会調査実習の試み」
- 「森田かずよ 世界に一つだけ、私の身体」を観ました
- 「伊豆の踊子」(1974)と「四季・奈津子」(1980)
- 名画座の打率
- 暗い眼をした女優─ミシェール・モルガン
- 『「千と千尋の神隠し」から考えるこれからの世界』
アーカイブ
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2009年8月
- 2008年10月
- 2008年8月
- 2006年8月
- 2005年8月
- 2004年8月
Count per Day
- 482852総閲覧数:
- 35今日の閲覧数:
- 409昨日の閲覧数:
- 村上春樹の「風の歌を聴け」のジェイズ・バー(映画ロケ地)
- タルコフスキーの『ノスタルジア』のロケ地を訪ねて
- 梅雨明けの虹でしょうか
- 小林秀雄の「山の上の家」
- ロンドンでカール・マルクスが住んだ家
- 吉祥寺、井の頭公園、噴水、大島弓子、ゾウの「はな子」さん
- タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』におけるラストシーンの動画
- 周防大島の上空
- 小津安二郎の世界-「東京物語」の尾道を歩く
- 柳川・地域づくり協力隊の阿部さん
- 著書・論文・報告書など
- 唐津小旅行
- 首里のあひる
- 信濃追分で、堀辰雄と加藤周一を歩く
- 2015年 「はかた夢松原の会」の「水と緑とまちづくり報告会」
- ベンツ6
- 九州大学社会学・安立ゼミの懇親会
- コレージュ・ド・フランス前のミシェル・フーコー広場
- 博多・灯明ウォッチングが始まります
- 今週の一押しポッドキャスト
カテゴリー
- トップ (1,659)