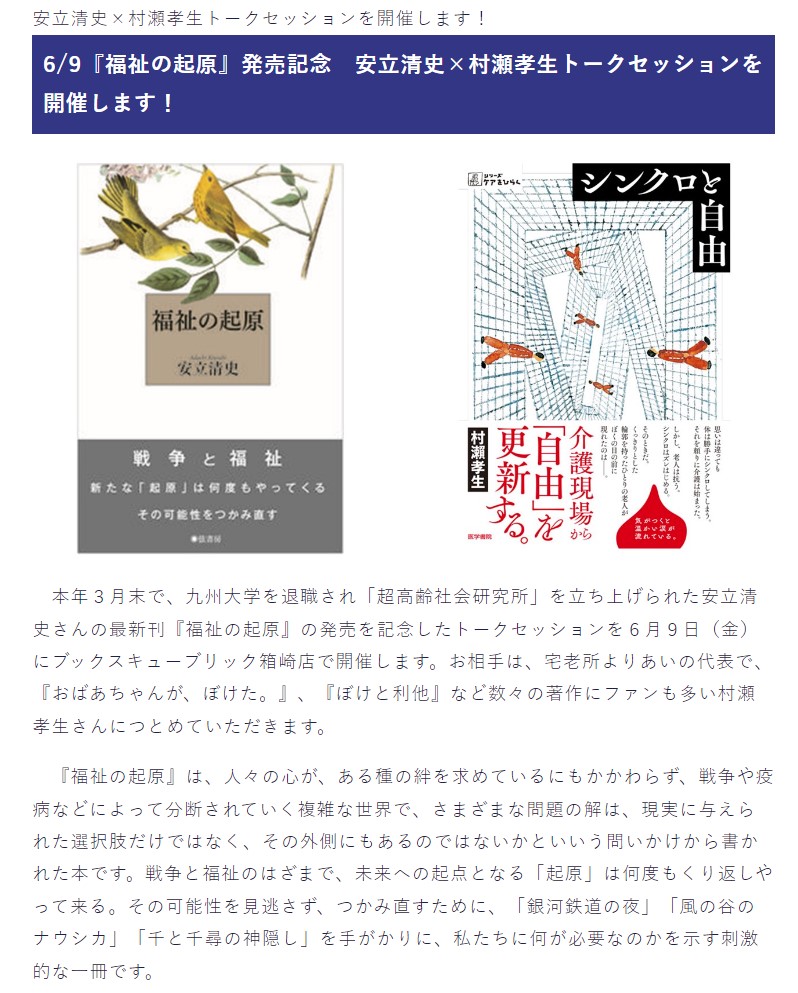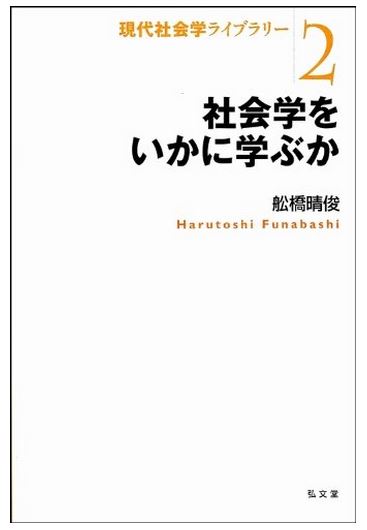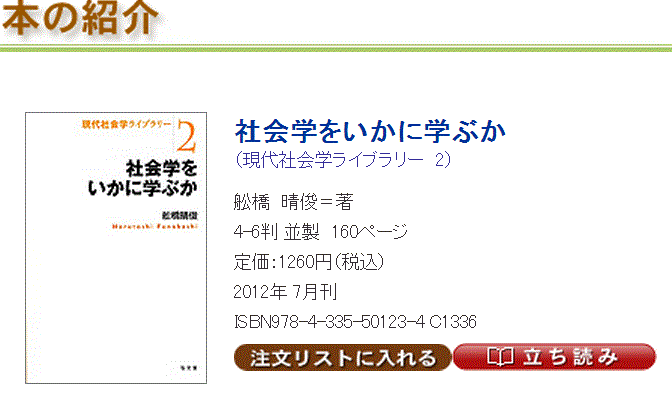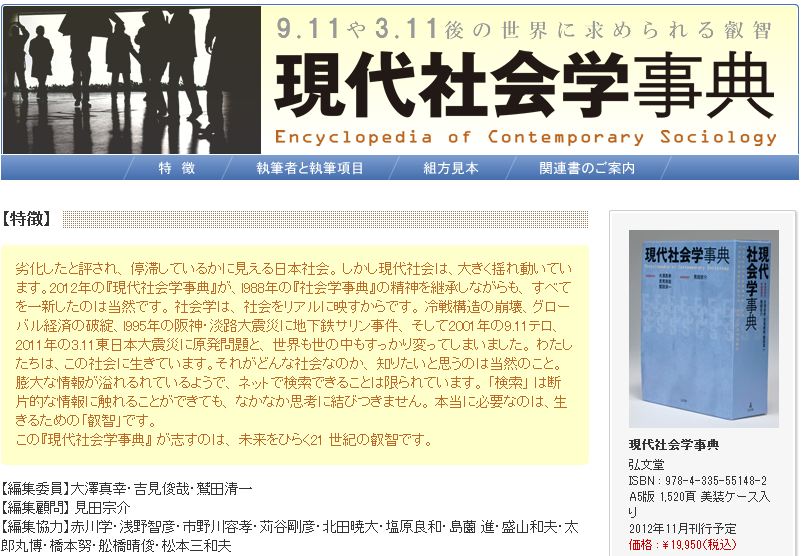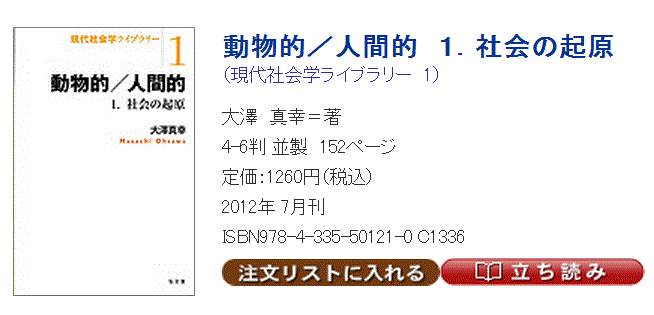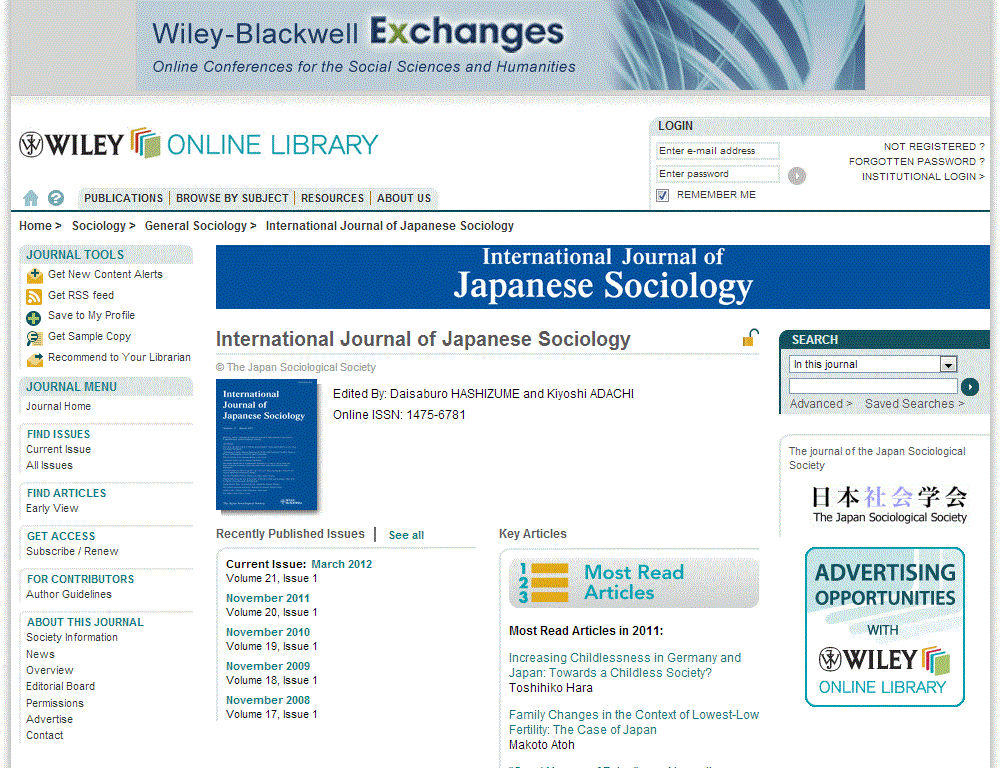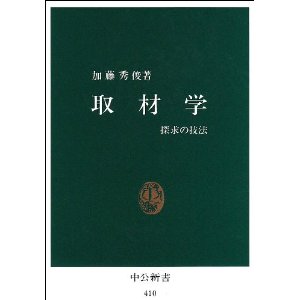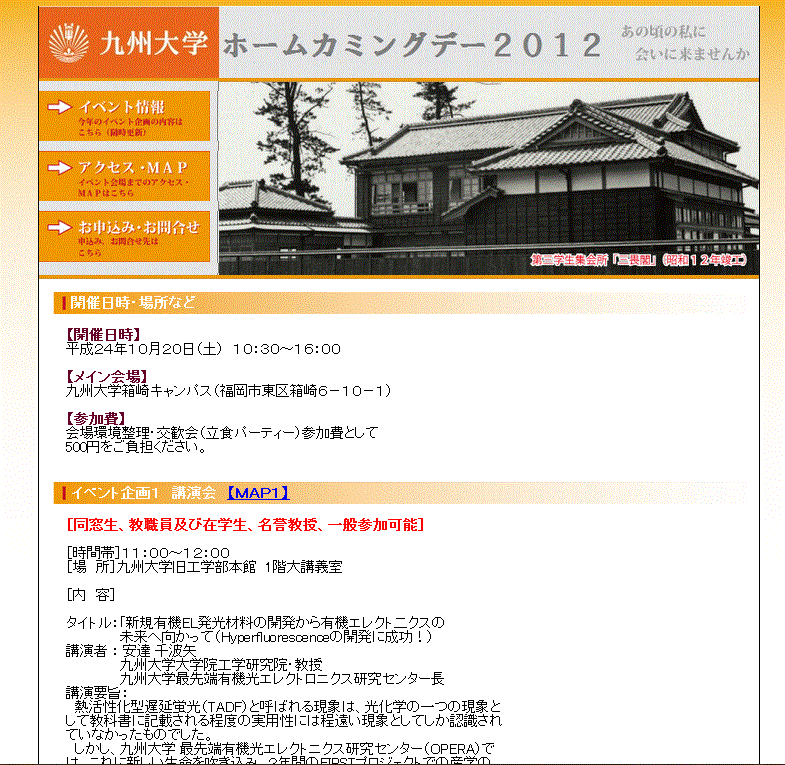ブックスキューブリックでのブックトークの詳細が決まりました。http://bookskubrick.jp/event/6-9
『福祉の起原』発売記念 安立清史×村瀬孝生トークセッション
日 時:2023年6月9日(金)19時スタート(18時30分開場)
会 場:カフェ&ギャラリー・キューブリック
(福岡市東区箱崎1-5-14ブックスキューブリック箱崎店2F・
JR箱崎駅西口から博多駅方面に徒歩1分)
出 演:安立清史、村瀨孝生
参加費(要予約):税込2,500円(1ドリンク付)
※オンライン配信も行います。
※終演後「サイン会」を開催いたします。
※終演後に同会場で懇親会あり(参加費2000円・軽食と1ドリンク付・要予約)
※参加費は当日受付にてお支払いをお願いします。
▼会場参加ご予約はこちら(税込2,500円・1ドリンク付き)
①Googleフォーム
https://forms.gle/4ywGwMXu8kMsMErH7
②Peatix
https://peatix.com/event/3586223/view